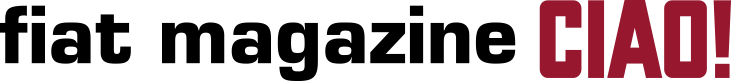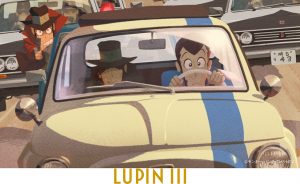イタリアの年末年始に欠かせない料理、ザンポーネとコテキーノってどんな味?
ザンポーネとコテキーノというイタリア料理をご存じですか? ザンポーネは豚足に、コテキーノは腸に、塩とスパイスを混ぜ込んだ豚肉のミンチを詰めたソーセージのこと。日本ではあまり馴染みがありませんが、イタリアでは年末年始に食べることの多い、冬の定番料理です。
ただ、この2品について調べてみると、ネット上ではなぜか「まずい」という評判が……。今回はイタリア各地の郷土料理に精通した、東京・池ノ上のイタリアン「ペペロッソ(PepeRosso)」の今井和正シェフに協力を仰ぎ、ザンポーネとコテキーノを実際に食べてみました。そのお味やいかに!?

「ペペロッソ」今井和正シェフ
イタリアの年末年始の食文化
— ザンポーネとコテキーノをいただく前に、まずはイタリアの年末年始の食文化についてお聞かせください。まずザンポーネとコテキーノが年末年始によく食べられているというのは本当ですか?
地方によって差はあれど、やはりイタリアの年末年始にザンポーネとコテキーノは欠かせません。発祥の地とされるエミリア=ロマーニャ州のモデナを中心に、イタリアの幅広い地域で食べられています。
ザンポーネは豚足の皮にミンチを詰めるので、手間もかかるし、皮に火を入れるのが難しい。だから家庭で作る場合、どちらかといえば火入れが簡単な腸詰めのコテキーノを作る人が多い印象です。近年ではプレコット(precotto)という、できあがっていて切るだけで食べられるレトルトタイプも主流になっています。
忘れてはいけないのが、ザンポーネやコテキーノには必ずレンズ豆を添えるということ。レンズ豆はコインのような形をしているので、食べるとお金持ちになるといわれているんです。験(げん)担ぎという意味では日本のおせち料理と似ていますね。
— ザンポーネとコテキーノの他に、年末年始に食べられているものはありますか?
クリスマスの食材でまず挙がるのがウナギです。ウナギは幸運な食材とされていて魔除けという意味で食べます。リゾットにしたり、グリルにしたり、揚げて南蛮漬けみたいにしたり。味はいいのですが、けっこう骨が入っていて、歯茎に刺さります(笑)。日本のウナギは下処理が世界一ですね。
塩漬けにした干し鱈のような食材、バッカラもよく食べられます。水で戻してパン粉をのせて焼いたりします。
そしてラザニアは絶対です。家庭ごとにオリジナルのレシピがあって、すごく大きいサイズで作ります。イタリアの家庭に入って修業させてもらったらまず、「お前のラザニアはなんだ」と聞かれるぐらい重要なメニュー。ここぞというときには必ずラザニアが出てきます。
あとはザクロ。ザクロはスーパーフードだと思われていて、エネルギーがつくとされている食材です。

写真左はウナギのグリル。ザクロも一緒に。写真右はラザニア。
パネットーネというパンと、パンドーロというパンケーキのようなクリスマス菓子もたくさん買って、1月の中旬ぐらいまで食べています。

ヴェネト州の老舗、ロイゾン社の超特大パネットーネ。大きいほど中がしっとりして、最高においしいとのこと。
— お酒はどのようなものを飲むのでしょうか?
地元のワインを飲んだり、あとはパネットーネとあわせてモスカート・ダスティというマスカットで作った甘いスパークリングワインを飲んだり。日本のお屠蘇(とそ)のように、お正月だからこれを飲むというのはあまり聞かないですね。
— お聞きしていると、クリスマスとお正月が一緒になっている印象がありますね。
ほとんど一緒です。だいたい12月に入ったら街全体がイルミネーションに包まれてクリスマスムード全開になります。各家庭でも飾り付けをして、小さいジオラマみたいなものを作り始めるんです。

— ジオラマを?
はい、みんな作っています。それ(キリスト降誕の様子を表した人形や模型「プレゼーピオ」)を家の目立つところに飾って、今年こんなにすごいのを作ったぞと、家を訪れた人たちと品評し合うんですね。
そんなことをしながら12月の中旬から1月5日ぐらいまでクリスマスのテンションが続きます。中でもメインは12月25日。日本では24日が恋人と過ごす日みたいになっていますが、イタリアでクリスマスは家族と過ごす日です。
年末のカウントダウンは広場に大勢の若者が集まって、そこでは花火が打ち上げられてみんなで盛り上がっています。
— クリスマスは家族と、大晦日は友人と過ごすんですね。
そうです。彼らにはキリスト教が根付いているので、クリスマスをすごく大切にしています。

ザンポーネとコテキーノの作り方
— では、いよいよザンポーネとコテキーノを作っていただきます。その前に一つ確認したいのですが、じつのところ「まずい」ですか?
そういう話はありますよね。みんなまずいと言うし、最初の師匠にも「ザンポーネは美味しくないからやらない」と聞かされていました……。これから作るので、実際に食べてみてください。
— ザンポーネとコテキーノのレシピはどこかで学んだものですか?
マルケ州とエミリア=ロマーニャ州のお肉屋さんで作り方を教えてもらいました。
発祥地であるモデナ産のザンポーネとコテキーノは原産地名称保護制度指定を受けているので、このスパイスをこのぐらい使うと厳密に決まっているのですが、その他のエリアだとオリジナリティあふれるものもありますね。今回作るのは比較的ベーシックで伝統的なレシピになります。
— まずザンポーネからお願いします。
じつは日本でザンポーネを作るのはかなり難しくて。ザンポーネは豚足のすねの部分にミンチを詰めるのですが、日本の豚足はくるぶしから下あたりで切られてしまっているんですね。イタリアだとザンポーネ用の豚足が普通に売っているのですが、日本だとまずお目にかかることはありません。
今回は知り合いという知り合いに連絡をとって、やっと沖縄からザンポーネに適した豚足を手に入れることができました。私も日本でザンポーネを作るのは初めてです。
❶ 皮の表面に残っている毛をバーナーで焼く。

❷ 皮と中の肉を分ける。皮に穴を開けないように注意しながら切り進めて足首まで分かれたら、すね肉を骨ごと断ち落として袋状に。

❸ 断ち落としたすね肉と少量の皮を細かく切り、塩、ナツメグ、クローブ、にんにく、パプリカパウダー、赤ワインなどを混ぜ合わせる。肉はミンサーで挽く場合も。

❹ 袋状になった脚部分を巾着のように絞れるように、皮の裾部分にタコ糸を通す。その中にスパイスと混ぜ合わせた肉をすき間なく詰め、端をタコ糸で絞って縛り、一晩水につけておく。

❺ 皮が破れないように、クッキングペーパーでくるみ、タコ糸を巻き付ける。3〜4時間、弱火で煮込む。

❻ レンズ豆は香味野菜と一緒に煮込んで、オリーブオイルとパルメザンチーズで味付け。茹で上がったザンポーネをカットして、レンズ豆と盛りつければ完成。

— 続けてコテキーノの調理もお願いします。
コテキーノの基本的な作り方はザンポーネと同じで、ザンポーネが豚足にミンチを詰めていたのに対して、コテキーノは腸にミンチを詰めます。
今回はプレコットという、湯煎するだけで食べられる加熱処理済みのレトルトタイプをご用意しました。イタリアの家庭でもよく食べられているタイプです。

ザンポーネとコテキーノを実食
それではお待ちかねのザンポーネとコテキーノをいただきます。ひと口ごとにレンズ豆をのせて、冷めないうちに口に運びます。

自家製ザンポーネは塩味も控えめで、ゴロゴロお肉がリッチな食感でたくさん食べられそう。プレコットのコテキーノはイタリア産の豚なので香りが強く、ワインがすすむのはこっちかも。
ザンポーネもコテキーノもスパイスが効いているものの、「これは苦手な人もいるよね」というほどの強いクセがあるわけではないので、まずいといわれている理由が分かりません。むしろうまいのでは?というか、かなりうまい。
「私もおいしいと思います。なぜ日本ではまずいと広がったのか」と、今井シェフも首をひねります。日本で最初に食べた人が、よっぽど質の悪いものに当たってしまったのでしょうか。
結論。
ザンポーネとコテキーノはおいしい。
※個人の感想です。
ペペロッソでは、この年末年始に自家製ザンポーネが提供されます。うわさ通りにまずいのか、それとも実はうまいのか……。ぜひあなたの舌でジャッジしてみてくださいね。

【取材協力】
ペペロッソ(PepeRosso)
〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目46−7 エクセル桃井 1F
TEL 03-6407-8998
店内 月〜土 10:00〜22:00
テイクアウト 月〜土 9:00〜22:00
日曜日・第1月曜日定休
ペペロッソ オフィシャルサイト

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
FIATの最新情報をお届けします。
RELATED ARTICLES
- CULTURE /500 /500C / ルパンがフィアットを愛する理由。『ルパン三世 PART5』浄園祐プロデューサーインタビュー
- CULTURE /Panda / 定番の魅力はさり気なさに〜パンダの底力「歴史とデザイン」
- CULTURE / イタリアと日本の文化を愛するイラストレーター、ビオレッティ・アレッサンドロの“POP・PRETTY・FUNNY”なメッセージ