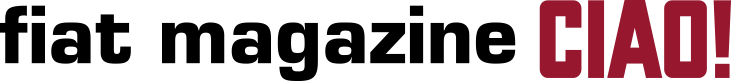“無名の偉人”木全ミツさんに聞く、公私共にうまくやるコツ
東大医学部を卒業し、労働省に入省。ワーキングマザーとして公務に尽力し、 労働官僚30年のうち15~6年を開発途上国に対する国際技術協力等国際関係の仕事に奔走、49歳で国連公使としてニューヨークに単身赴任。その後、ザ・ボディショップジャパンの初代社長に就任。のちにNPO法人「JKSK 女性の活力を社会の活力に」を設立、日本やアジアにおける女性のリーダーシップの育成に尽力されるなど、数々の輝かしい実績を積み上げてこられた木全ミツさん。その生い立ちや実績は、『仕事は「行動」がすべて 無名の偉人・木全ミツの仕事』(伊藤彩子 著 WAVE出版)に綴られています。
この本で“無名の偉人”と表現されているように、木全さんは表に立って采配を振るうというよりは、後ろから押すタイプ、というのでしょうか。周囲の人を巻き込み、取りまとめて大きな力を生み出し、プロジェクトを成功に導いています。フィアットとは、Share with FIATの活動を通じ、東日本大震災復興支援プロジェクト(関連記事)や、アジアの優秀な女性に教育の場を提供する活動(関連記事)などに共に取り組みました。今回は木全さんに豊かな経験をお持ちの大先輩として、仕事や日常をスムーズにこなすコツや、意識の持ち方についてアドバイスを伺っていきます。
自立心が芽生えたのは9歳の時
──まず率直にうかがいたいのですが、木全さんはなぜそんなに優秀なのでしょうか?
「優秀と言われますけど、私は子どもの頃、ごく普通の女の子でした。兄弟姉妹が9人。6人が男の子、3人が女の子で私は次女。誰からも期待をされていない、どうでもいい普通の女の子であったと思います。兄や姉は優秀で、常にクラスで一番だった。でも私は、 “クラスで一番”ということにあまり関心を持ってませんでした。1番をとったこともありますが、常にではなかったので家庭内ではデキが悪いと思われて、親から期待される子ではなかったのではないでしょうか」

木全さんが9歳のとき、その後の人生に大きな影響を与えたという出来事が起こります。木全さんのお父さまは第二次大戦のとき陸軍の軍医大佐をされておられ、木全さんが小学生の頃、家族皆で満州の新京(現在の中国の長春)に移住。侵攻国の軍の幹部として、なんでも手に入るような生活を送っていたそうです。しかし、そんな生活に変化が訪れます。戦局が悪化すると木全さんのお父さまは子どもたちを集めて、次のように伝えたそうです。
“いいか、これからはお母さんのいうことをよく聞いて、日本に帰って生活するのだ”。お母さんと子どもたちは、その地に残る父を心配しながらも言われるがまま満州を後にしました。
「満州を離れて、朝鮮半島を汽車で移動していきました。1945年8月15日、日本が敗戦したという報を一家は今の北朝鮮の首都,ピョンヤンで聞きました。日本の敗戦を知った朝鮮の人たちは、それを喜び、日本から痛めつけられてきたことに対する怒りをあらわに、“憎き日本人を殺せ!”と暴動を起こし、私達日本人に襲い掛かってきました。その時、私たち家族の面倒を見てくれていた父の部下の軍部の人が、“この穴に入りなさい”とおっしゃり、母と一緒に真っ黒い穴に入りました。やがて、ガタンという音と共に穴の入り口が締まり、その後、ゴトン、ゴトンという音と共に動きだしました、当初はわからなかったけれども、それは石炭を運ぶ貨車だったのです。その貨車に人間が乗っていることは疑われず、無事に朝鮮半島を後に、舞鶴にたどり着きました。満州からの引き揚げ船の第一号でした。たどり着いた日本は焼け野原、浮浪児がごろごろとした状況でした。母と一緒に福岡・久留米にたどり着きました。その頃、母のお腹には8人目の子がいました。久留米では、生活力のない母のもと、どん底の生活を強いられました。母は日本の陸軍大将の妻になるというのが夢でした。でも敗戦後の彼女の生活は、生活保護を受けながらのぎりぎりの生活でした。国家を信じ、夫を信じて生きながら、将来は日本の陸軍大将の妻になるという夢のはしごを、自分の力とは関係のないところで外された、哀れな母でした。子どもたちはお腹が空いたといって母を苦しめると、母は配給されたかぼちゃの一切れをお皿にのせ、“まだ、夕食には、時間が早いけど、食べたら動かないのよ、お腹が空くから”と言いました。“ああ、いやだいやだ、あんな哀れな女にはなりたくない。私は、どんな時代、どんな環境に置かれても自分の二本の足で立ち、歩んでいく人間になりたい”と、本当にそう思いました。それが私の自立心の基本であり、職業意識の芽生えでした。9歳の時です」
戦時下での混沌のなか、児童期に天と地のように違う生活を経験したことを振り返ってくださった木全さん。そうした経験も糧に“偉人”となったご自身のスタイルを3つ挙げてもらいました。
1 誰にも頼らないで生きていく
「どんな時代、どんな環境下に置かれても、誰にも頼らないで生きられる人間になりたい。9歳の時に強く思ったその気持ちは、その後ずっと変わっていません。自立するということは、まず、経済的にひとり立ちするということです。ですから私はひとりでも生きられるように就職して収入を手にするようになって以来、今日まで収入の20%を貯金することを原則として守ってきました」
2 何事も自分で決める
「もうひとつ大切なことは、“自ら選んだ道、自分が決めたことではないか”という考えです。それが自分の人生を支えてきました。進学の際の専攻、職業の選択、結婚の決定も、誰からの推薦、アドバイスでではなく、すべて自分で決めました。そして誰からも強制されたものではないからこそ、自分で責任が取れるのです。言い換えると、決定したことがうまくいかなくても“貴女が自分で決めたことではありませんか”ということが背中をおしてくれ、勇気をもって対峙してきたことにより、問題を解決していけたのだと思います。自ら行動をとることの重要性。私はこのことを、人生を通じて学んできました。だから人生でなにひとつ後悔はありません」
3 どんな経験や体験も自分の血となり肉となる
「人はそれぞれ違う体験をして生きていきます。なかには、反り(そり)が合わない人もいるでしょう。でもそうした人とも一緒に物事を進めていく、という場面は仕事においても日常でも多々あります。そのようなとき、嫌だなと思ってやるのと、前向きに受け入れて進めていくのでは大きな違いが出てきます。後述しますが、どのような人でも、自分にはない優れた一面を持っています。それぞれが持っている“良さ“とお付き合いをしていこう、自分なんか大した人間ではないと。そうした相手との経験から何を学ぶか。そしてそれを血として肉とすることで、人生の豊かさは変わってくるということを学んでまいりました」

──職場のなか、組織のなか、あるいは家庭のなかであっても、自分の信念が周りの人々の考えと対立したり、価値観の違う人とぶつかったりすることはあると思います。そのような時は、どのように折り合いをつけるのでしょうか?
相手のすばらしい面とお付き合いする
「相手は自分が気に入らない点を持っているかもしれませんが、自分にはない良さが必ずあります。私は、相手のその良さとどうやって付き合って行こうかということを必死に考え、そのすばらしさとお付き合いしていこうと心掛けてきました。もし相手とぶつかった時、非難したり、罵倒したりして、された人はハッピーでしょうか? また罵倒した本人はそれでハッピーになりますか? そんなことをしても上手くいくわけがない。自分と意見が異なることがある場合、必ずそこに理由があるので、その理由を冷静に考え、解決する努力をした方がずっと早く、良い方向に向かうのではないでしょうか。そしてその経験は自分を成長させてくれ、その後の実績をあげる力になるのだと思います」
──仕事の話になりましたので、もう少しお聞きしたいと思います。仕事やプロジェクトを進める際に大切なことはなんでしょうか。
1 どんな仕事も自分ひとりで成し遂げることはできない
「私はどんな仕事やプロジェクトもひとりでできることはないと思っています。だから、成し遂げた結果に対して、これは誰それの功績だという言い方も適切ではないと思います。個人だけでできることというのは、あっても小さいのではないでしょうか。“自分はたいしたものではない”と自覚するべきだと思いますね。賛同者がいて、共感する人がいて、価値観を共有できる人々がいて、それで一緒にやっていこうと繋がった時に大きな力が生まれるのだと思います」
2 自分の考え、方針を明確に打ち出すことは大事
「ただし、チームでプロジェクトを進めていくときに、私はこういう考えであるということは、押し付けではなく、相手にお伝えすることは重要だと思います。その考えが他の方と同じでなくてもいいんです。賛同が得られることもあるし、意見は違う場合はまず耳を傾け、理解し、ひとりひとりを大切にすることが大切です。そして、自分が誰よりも一番働くことに努めてきました。そうすると周りの人はその姿を見て、自分のやることを考えて動いてくれますから。会社だったら社長、プロジェクトだったらそのリーダーが一番の小使に徹するべきだと思いますね」
3 成果を同志とともに分かち合い、喜び合う
「そしてその仕事を成し遂げたら、喜びを一緒に分かち合う。それが次のエネルギーになるのです。私も同志を家にお招きして手料理を振る舞ったり、お酒を一緒に飲んだりします。実感を分かち合える場を作る、ということは、とても大切なことではないでしょうか」

不可能なことはない
──これまでのお話でもわかるように、木全さんは個を尊重し、人を大切にされます。そして人から頼まれたことは断らないといいます。なぜなのか。うかがってみました。
「There is no word of impossible in my dictionary。私の辞書には不可能という言葉はない。なんでもやってみるべきだと思います。したがって人から頼まれて断ったことはありません。小さなことでも大きなことでも、やればやれると思っています。成果に差はあるかもしれないけど、まずはやってみることだと思いますね」
「戦後の混乱のなか、私たち子どもたちは食べるものがなく、みんなお腹を空かしていたお話をしました。そういう生活をしていたとき、軍部で父の部下だった方が時々、様子を見にきてくれていました。私は母にお腹が空かない生活をするには、月にいくら位必要なの? と聞いたことがあります。“3,000円くらいあればねえ”いう母の言葉がずっと耳に残っていました。小学校をあと2年、そして中学3年間を終わらないと働くことができないと思い込んでいましたが、訪ねてきたおじさんに、“早く、義務教育を終え、お金を稼ぎたい、母を助けたい”と心情を伝えると、“お嬢ちゃんにもできることはありますよ。パンを9円で仕入れて12円で売りなさい”と。そして、おじさんがパンの仕入れを手伝ってくれ、私は一軒一軒訪問しました。“パンを買ってください”、“いくらなの?”、“12円です”、“高い、10円にしなさい”、“10円にしたら、わたしの儲けがなくなります”という会話を交わしながら、毎週日曜日に、100個を目標に売って歩いた。数ヶ月実行し3,000円を貯めて母に渡したら、最初は泣いて受け取ってくれませんでしたが、最後に喜んでくれた。その時のことは、今でも鮮明に覚えています。子どもが多かったので、すべての子に目を配ることもできなかった母でしたので、母は私の訪販の体験には気が付いていなかったようです。その時、私は“やればできる。人生に不可能なことはない”ということを学びました。小学4年、10歳の時です。そして、この体験から得た信念が、私の人生の屋台骨の一つとして今日まで支えてくれています」

──人のために尽くす。木全さんのそうしたお考え、そしてこれまでの実績をみると、自分のためではなく、社会のため、あるいは少し大げさかもしれませんが、世界のために働いているというか、そういう意識を感じます。
「自分のためじゃなく、日本人として、アジアの一員として、世界の一員として行動する、という意識は常にあります。大学の専攻で公衆衛生を選んだのも、そのような理由からでした。当時、医者にかかれる人はまだ少なかった。そんな時代でした。医者にかかれる数人のために働くのではなく、医者にかかれない大勢のことを考えて生きたい。それが“社会のため”という意識を持つようになった始まりでした。父も応援してくれました」
「シベリアに抑留された父には、“家族は、全員、朝鮮半島で皆殺しにあった”という報が届けられていたようです。“すべての家族を失った自分には、帰国をする理由がない、若い将来のある部下たちを優先的に帰国させよう”と心に決め、部下たちを優先的に、シベリアからの引き上げ船に送り込んでいた。他方、子どもの私達は音信不通の父について、生死もわからない中で、父に手紙を送り続けました。そのうちの一通が父に届いたようです。子どもが日本で生きていることを知った父は、最後の引き揚げ船で帰ってきました。一人でも生きていればという思いで帰ってきたら、皆生きていたという喜びの中で、父は子どもたちを前に、“俺は、社会的地位も、名誉も、財産も失った。しかし、諦めていた子どもという宝があるじゃないか。私は医者だ。再起可能だ。日本に将来があるとすれば、それはテクノロジーだ。これからの日本の社会には、男も女もない。能力があるなら大学に行け。そして専攻は理系を選べ”と。さらに、“ひとつだけお父さんに協力してほしい。国立大学に進んでほしい”と。私が中学2年の時でした。そして、後に東京大学の医学部で公衆衛生を学ぶことにいたしました」
家庭内の問題をスムーズに進めるコツ
大学時代に勉学に励んだ木全さん。そこでご主人となる方と出会うこととなりました。
「夫は、医学部の3歳年上。彼からラブレターをもらいました。私は、21歳、恋だ、結婚だ、などということはまったく眼中にもなく、そんな気持ちのかけらもなかったころです。“九州から東京まで出てきて勉強しているのは、伊達や酔狂ではない。勉強以外のことに時間を取られたり、エネルギーを注いだりしたくない、理解していただきたい“ といったような内容の返信を送りました。しかし、ある日、同じサークル(ソヴィエト医学研究会)の活動を終え友人たちとワイワイ言いながら本郷のキャンパスからお茶の水駅まで帰っている時に、今まで避けていた彼と視線がぶつかった。どういう訳か、胸の高まりを覚えた。そのことを私の女友達に話したら、彼女は後で彼に “脈なしにあらず”と伝えたようです。その友人の計らいが発端で、私達のデートが始まりました。結婚まで3年半お付き合いを経ましたが、デートの時はいつも、“私は自分の道を自分の足で生きていく”ということを必死に伝え、ディスカッションも重ねました。その結果、120%理解をし合い結婚することになりました。結婚してやがて60年になりますが、今日に至るまで、ケンカもなく実にうまくいっています。夫の人間性の素晴らしさもあり、お互い尊重し、感謝し合う。そんな関係を築くことができています」

──ご主人のお話が出ましたのでお聞きします。家庭をうまくいかせるため、相手とぶつからないでうまくやっていくには、どうしたらよいとお考えですか?
1 ひとりの人間として相手の人格を尊敬、尊重する
「これは夫婦に限らずですが、ひとりの人間として尊敬・尊重することは大前提だと思います。私の場合、結婚を前提とした夫との3年半のお付き合いの中で、私の生き方の姿勢を理解してもらいました。私は“あなたに付いて行きます”、なんていう人に本当の魅力を感じられますか。自分の道を持って、一生懸命生きる。それが魅力なのだと思います。そして結婚するからには、お互いを讃えあう。そのスタンスがとれればケンカなんて起きません。時間はいくらあっても足りない、そんな中でケンカに費やす時間などありませんよね。もったいなくて……」
2 結婚後は、1日に1-1.5時間は意見交換の時間を
「結婚してルールを決めたのです。1日に1-1.5時間は意見交換の時間を作ろうって。そして1週間のうち1日は仕事を離れて過ごそうと。そして1年間に1週間はニッポンを、世界を旅しようと。官僚というのは毎日、夜中帰りなのよ。彼も東大の先生でものすごく忙しくて、そんな生活だけど、できれば1日のうち、お酒飲みながら1時間から1時間半はお話をしようということにしたんです。テーマは、日本やアジアの社会問題、経済問題、外交問題、国際関係、スポーツ、芸術とか、そういうテーマに絞りました。家庭の問題、例えば息子、姑、近所のことなど、そういう話は一切しません。家庭の問題って、話しても何もいいことないんです。解決能力がない人がしても不愉快になるだけ。夫に最愛の姑さんのお話をして、問題が解決できると思いますか? 答えはN0ですよ。事態はますます不愉快になるだけではないでしょうか。だから初めから話題にしないことですね」
3 義理の親との関係について
「嫁・姑問題については、私はこういう経験をしました。夫の両親とは同居で、出産したとき義母にとって初めてのかわいい孫でした。それでフワンフワンの布団を作ってくれたんです。でも骨が発達していない赤ちゃんは、本来、固いところに寝かさないといけない。そのフワンフワンの布団に寝かせて息子の背骨が丸くなったらどうしよう……と夜も眠れないくらいに心配でした。一度、夫とそのことをテーマに話し合いました。彼は、“母の気持ちを考えて、感謝するしかないんじゃないか”と。それで私は思いました。話をしても無駄だと。その時から家庭のことをテーマにしないことにしたんです。だからといって“お母さま、柔らかい布団に寝かせると子どもの骨が……”、とかそんなくだらない言い方はできません。私が面倒を見られない時間帯は仕方ないと割り切り、目を瞑ろうと。でも私がいる間は硬い布団に寝かせると決めたのです」
「もうひとつ、こんなエピソードがあります。木全の母は、お茶の先生をやっていて、同居して住みはじめた最初の日曜日。“あなた、お茶をなさらない?”と声をかけられました。1日じっくりと習い、“なんとすばらしい茶道の世界……”と実感しました。母からは、“あなたは吸収がはやく、頭がよろしいわね。茶道なさらない?”と言われました。でもその時に閃いたんです。これはいけない、と。私が茶道の道に入ったら、いい加減にはやらないから、いつか母を追い抜いてしまう日が来るかもしれない。母と競い合うという機会は絶対に避けなければならないし、必要なことではない。このお誘いは受けてはいけないと。この決断は結果的に大成功でした。母は毎月、お茶会を我が家のお茶室を使って開催しますが、その準備は大変なんです。でも私はそこには立ち入らず、お手伝いもしない。一方、同居を決定した後、我が家にホームバーを作って、20人くらいの内外のお客さま達をお招きして、私の手料理でおもてなしを頻繁に行います。その準備におおわらわしている私を見て、母が“お手伝いしましょうか?”と言ってくださっても、“いえいえ、お母さまはお客さんと一緒に参加して下さい”と伝えます。こうして私の世界は私の世界、母の世界は母の世界として、大切に守り続け、お互い尊敬し合い、感謝しながら生活できてきました。結果的に最後の寝たきりの10年間を含め、“同じ屋根の下で……”を合言葉に素晴らしい50年の同居生活を過ごすことができました」

──公私それぞれのことについて、アドバイスをありがとうございます。最後に女性へのメッセージをお願いできますでしょうか。
「日本の社会は大きく変わってきていると思います。政府は今日でも、例えば、国民が関心を持っている年金問題について説明する折に、“夫が40年働き、妻が専業主婦”というモデルケースについて、という表現を使いますが、なぜ、この時代に、専業主婦の家庭をモデルとするのか疑問を禁じえません。かつては結婚したら夫が家計の責任を持つ、ということがあたり前であるとされていましたが、高齢化がどんどん進んで行っている今日、両親の老後のお世話はもとより、結婚して50-60年間、子供たちの教育、養育、自分たちの健康な生活の維持のすべてをカバーする経済的負担を夫1人の責任にすることなど、非現実的です。現実的にも、“俺についてこい”、なんて言い切れる男、それを実践できる人が果たしてどれだけいるでしょうか? 私は、たったひとつしかない自分の人生を、国にとか夫にとか男に頼って生きていこうとするのでは、ご自分の本当の幸せはつかめないと思います。そうではなく、結婚しても、家族の一員として責任を持ち、自分の自立した生き方をしっかりと持ちながら、夫にも子どもたちにも、自立した生き方を推奨し、その上で、お互い生き方を認め合い、尊敬しながら、良さを発揮しながら響き合って生きていく、その指揮官になっていっていただきたい。すなわち、自分の幸せな人生を、誰かに頼るのではなく、自ら引き寄せていって、初めて実現できるのではないかと思っています。そういう気持ちを持って、本当にひとつしかないご自分の人生を素敵に、大切に構築していっていただきたいと願っています」
今日はどうもありがとうございました。
文 曽宮岳大 撮影 宮門秀行
フィアットがすべての女性にエールを送るプログラム#ciaoDonnaの詳細はコチラ

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
FIATの最新情報をお届けします。
RELATED ARTICLES
- NEWS /500C / がんばる皆さんにフィアットからCiao!とミモザを。ホワイトリボンラン2018
- CULTURE / “チャオドンナ”が合言葉!女性による女性のためのフィアット試乗会は「楽しい、かわいい!」
- NEWS / 女性の力を、より良い社会へ。国際女性デー記念企画