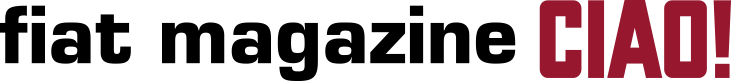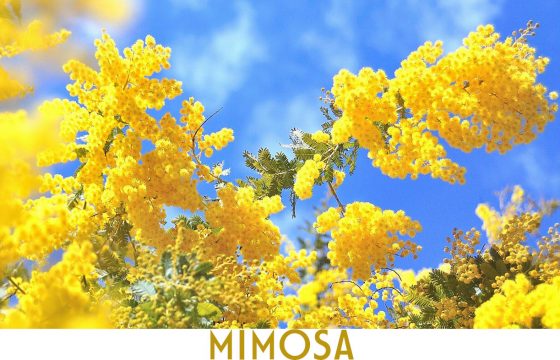重い病気の子どもたちと笑顔を共有。スマイリングホスピタルジャパンの活動とその思いを聞く。
#Share with FIAT#スマイリングホスピタルジャパン笑顔は子どもの無限のパワーに 病院や施設で病気と闘っている子どもたちや、在宅医療を受けている子どもたちを訪れ、アートや音楽などの芸術活動や学習を通じ、子どもたちと豊かな楽しい時間を共有する活動を行っているNPO法人スマイリングホスピタルジャパン。その代表理事 松本惠里さんにお話をうかがいに、設立されたばかりの新事務所を訪れました。コロナ禍で病院訪問が難しくなってしまったこの時期に、“できないこと”について考えるのではなく、“できること”に目を向け、全力投球されている松本さん。2021年6月には著書『夢中になれる小児病棟 子どもとアーティストが出会ったら』を出版されました。書名にもある“夢中になる”とは、どういうことなのでしょうか。松本さんにうかがっていきます。 スマイリングホスピタルジャパンでは、面会が保護者のみに限られている小児病棟に、アーティストと共に訪れ、子どもたちにアートや音楽に親しんでもらう活動を行っています。闘病生活で直面する辛い治療や活動制限、生活体験の不足によるストレスや不満を少しでも取り除き、ふさぎがちな気持ちを明るく開いてもらいたい。そして闘病意欲を持ち続けられるように支援したい。活動にはそんな想いが込められています。そうしたなかコロナ禍が襲い、病院への訪問は困難になってしまいました。子どもたちは両親と会える面会時間までもが減ってしまっているそうですが、そんな時期だからこそ、子どもたちに楽しみの時間を届けたい、というのが、松本さんはじめ、スタッフやアーティストの方の想い。現在は訪問活動の代わりにアーティストの方と協力して、塗り絵や紙芝居セット、ステッカーといったプレゼントを贈っているほか、YouTubeの『スマイリングちゃんねる』を通じて、マジックや音楽遊び、実験など手や体を動かして楽しめるアクティビティを提供し、子どもたちが笑顔になれる機会の拡大を図っています。また、病棟や施設をオンライン訪問し、双方向のライブというかたちでアートを届ける取り組みも始めています。 ―松本さんは、かつてご自身が交通事故に遭われて入院生活を余儀なくされ、その後、院内学級で教員をされていて、そうした経験が現在の活動の原点となっているということですが、そのあたりの経緯についておうかがいしてもよろしいですか? 「はい、今から20年ほど前に生死の境をさまようような交通事故に遭い、長期の入院生活を送りました。思うように身体を動かせず、その先にやろうとしていたことが全部できなくなってしまうのかという思いと、将来への不安でどん底の気持ちでした。事故に遭う前は、英語が好きだったので教員免許を取りたいと思い、通信教育で勉強をしていたんです。事故後も通信だから家で勉強できるのだけれども、手が動かなくなり、身体も痛いからもうやめようと思っていました。でも、退院して何かがフっとおりてきて(笑)、辞めずに続けるべきだと何かに押されるような思いで、なんとか単位をとって教育実習も受け、教員免許も取得したんです。それで初めて配属されたのが病院の中の学校、院内学級だったんですね。自分は長いこと入院生活を送っていたので、その経験がなにかに生かせるのではないかと、病院で難病と闘っている子どもたちに教える導きかもしれないと思いました。院内学級では英語を教えていたのですが、子どもたちと時間を共に過ごすなかですごく心に響いたのが、子どもたちの笑顔でした。病気と闘っていて辛いはずなのに、そんな時でも笑顔を見せてくれる。病気が辛くて大変なのに勉強も頑張っていて、お友だちにもとても優しくて、そんな子どもたちから大切なことを教えられる毎日は素晴らしいなあと感じました。職員室よりも病棟で過ごす時間が長かったほど、子どもたちと過ごす時間が大好きでしたね。院内学級には7年間いて、そのあとに今までの“気付き”を何かかたちにしようと思い、この団体を立ち上げたのです」 聞こえなくても心の声に耳を傾ける ―その院内学級での“気付き”について、少し詳しく教えていただけますでしょうか。 「重たい病気と闘っている子どもたちが、ふと笑顔を見せてくれる。ではどんな時に笑顔になるんだろうと着目してみると、自分らしく活動できている時だというのがわかってきたのです。自分らしく活動している。それは芸術活動をしている時。音楽や絵を描いたり、歌を歌ったり、そういう情操活動をしているときが子どもたちはイキイキしていて、いい表情を見せてくれていたのです。それでこういう活動を特化して行う団体を作りたいなあ、という思いに繋がっていきました。そうして立ち上げたのがスマイリングホスピタルジャパンで、芸術活動を病院に届ける活動から始めました。楽しいことに夢中になる。そうした経験を通じて、心が自由になる時間を持ってもらいたい。私たちの活動の軸としているのは子どもたちが体を動かしたり、声を出したりして一緒に楽しめる参加型の芸術活動です。今やっているオンラインでの動画配信でもそれは同じで、子どもたちが一緒に楽しめるプログラムの制作を心掛けています」 ー病院への訪問やオンラインでの動画配信やライブに加え、在宅訪問もやっていらっしゃいますが、在宅訪問についてもうかがえますでしょうか。 「在宅訪問は、病院にアートを届ける活動をしているなかで派生していった活動です。病棟には小児がんの難病だったり、けがをしていたり、いろんな子どもが入院しているのですが、なかには重度の肢体不自由のお子さんがいます。そうしたお子さんは、音楽やマジックなど、こちらからの働きかけに対して、感情を自分から表出できないこともあります。でも機会は平等に届けたいと思っています。通常、私たちが病院を訪れると、動けるお子さんにはプレイルームに集まってもらい活動をするのですが、そこに来られないベッドでずっと寝ているお子さんの場合、ベッドで安静にしながらであれば大丈夫な場合は、スタッフがベッドごと連れてきてくれたり、あるいはベッドサイドから離れられないお子さんのところには、保育士さんやスタッフに案内してもらい、ベッドの前で活動を行ったりすることもあります。しかし重度のお子さんの場合、処置やお風呂の時間でもないのに取り残され、我々の活動に参加させてもらえないことがあるのです。“この子達は、たぶん、わからないだろう”とか、“聞いても感じないだろう”と思われてしまっているのだろうか。さらにその子たちが退院してお家に帰った時に、何か活動はあるのかな?と思ったんです。それで特別支援学校の教員に相談してみたところ、学校でも個別に活動を提供できる機会というのは少なく、それが課題になっていると教えて頂いたんです。じゃあ、そういう子どもたちのところに訪問する活動を始めようじゃないか、と。子どもたちは自由が制限されて困難な状況でも、“もっと何かやりたいよ”という気持ちが潜在的にあることはわかっていたので、障害が重そうに見えても、たとえ反応はできなくても、絶対に何かを感じてくれているはずだと。そういう感触はありましたから、見た目で判断して何もしないのは違うと思ったし、差別でしかないと思ったので、そういうお子さんにも手を当てていこうと思い、在宅訪問を始めました」 子どもの成長機会を保障する ー新しい事務所を設立されたのも、そうした活動範囲の拡大や変化と関係しているのでしょうか。 「これまでは自宅の一部を事務所にして活動してきたので手狭になってきたというのもありますし、事務所が自宅だとどうしてもお客さんに来ていただくのが難しかったりするので、色々な方に来て頂いたり、集まってもらえる場所を作りたかったのです。新事務所では、アーティストさんたちが来てリハ―サルをしたり、打ち合わせしたりできますし、動画配信の収録やオンライン訪問によるライブもできるようになりました。また、在宅医療を受けているお子さんは、家に閉じこもりがちになってしまうので、体調の良いときは出かける先としてここに来てもらい、学習室として使ってもらっています。また、在宅医療で使う教材もうちで手作りしているので、工房が欲しかったんです。在宅医療の教材というのはお子さんの状態に合わせて作っていくんです。お子さんによっては、指先が少ししか動かなかったり、最重度のお子さんは、ベッドに寝た切りで沢山の管がついていることもあったりするので、そういう子にはスイッチ教材という自分で主体的に動かしフィードバックが得られる教材や、量や空間の概念を身につけられる感覚教材を使ってもらうんです。工房があることで教材が作りやすくなりました。永福町の駅の近くなので、子ども連れのご家族やご高齢の方が立ち寄ってくれたり。いろんな方との出会いを生んでくれています」 ー最後に、2021年6月に『夢中になれる小児病棟 子どもとアーティストが出会ったら』を出版されましたが、どのような本か簡単にご紹介をお願いできますか。 「この本は、団体を立ち上げた想いや経緯を綴った本になっています。普段からブログでも綴っていたのですが、本で一番伝えたいことは、難病でも障害が重たくても、コロナのような事態になっても、子どもというのはどんな状況でもいつでも成長し続けています。だから学びや活動をストップさせてはいけない。どんな事態でも、大人は子どもの成長する機会をできる限り保障していかないといけない、ということを発信していきたいと思っているのです。子どもたちが情操活動や夢中になれる活動をすることで、本当に豊かに成長していく姿をずっと見てきました。そのことを知ってもらいたい。また、この本を読んでいただくことで、ぜひうちでも、という病院がありましたらご連絡いただきたいですし、アーティストやボランティアとして活動してみたいと思ってくださる方がいたら声をかけていただきたいです。」 なお、『夢中になれる小児病棟 子どもとアーティストが出会ったら』は、英治出版から発売中です。Amazonなどで電子書籍版も用意されていますので、ぜひのぞいてみてください。 スマイリングホスピタルジャパン公式WEBサイト https://smilinghpj.org/ フィアットが大切にしているシェアの気持ち 「Share with FIAT」 Text/ Takeo Somiya(Fresno Co., Ltd.) […]
ASHOKA JAPAN 社会問題に取り組む若きチェンジメーカーをサポート
#ASHOKA JAPAN#Share with FIAT行動力と、失敗しても立ち上がる忍耐力 1980年に歴史家・法律家であるビル・ドレイトン氏により創設された世界最大の社会起業家ネットワーク、アショカ。社会起業家とは、アショカの言葉を借りると様々な社会問題の抜本的な改善を図り、根深いグローバルな課題を生み出している仕組みそのものを変革する人のこと。アショカはこれまでに数多くの社会起業家を輩出していますが、世界中で次々に起こる社会問題に対し、その改善に取り組む人、チェンジメーカーの数は圧倒的に不足しているといいます。そこでアショカでは、12歳から20歳までのチェンジメーカーの素質がある若者を見つけ、支援する“アショカ・ユースベンチャー”の取り組みを展開しています。 アショカ・ユースベンチャーでは、1年間の実験環境を通じて、彼・彼女らが向き合う社会の問題に、自らで解決策を見つけてアプローチしていく機会を提供しています。そのユースベンチャーを認定するために3月6日(土)に開催された、第43回パネル審査会の模様をリポートします。はたして、若きチェンジメーカーは社会問題にどう向き合い、どのようなアプローチで問題の解決を図るのでしょうか? 今回のパネル審査会では、18才と19才の計3名がプレゼンテーションを行いました。今回はそのうち、山内ゆなさんのプレゼンにフォーカスしてお伝えします。彼女は、児童養護施設のことを多くの人に知ってもらい、情報が限られている施設に住む子どもたちに本を届ける活動を行っています。その活動をさらに発展させるべくアショカ・ユースベンチャーを目指します。 パネル審査会では、ユースベンチャー候補者の認定を判断するパネリストとして、3名の有識者が就きます。今回は豪資源大手BHPの日本法人の代表を務められているガントス有希(ゆき)氏、京都大学大学院教授の寶馨(たから かおる)教授、シンガポールに本拠地を置くベンチャーキャピタル、リープラベンチャーズの佐藤克唯毅(さとう かつゆき)氏の3名が務めました。 アショカがユースベンチャー審査において重点を置いているのは、「内発的動機」、および「行動力とレジリエンス」です。内発的動機とは、心の内側から来る動機のこと。つまり周りに認められたいからやるというのではなく、自分が本当にやりたいと思っている活動であるかという点です。一方、「行動力とレジリエンス」は、失敗したときに他の方法で試したり、もういちど試してみたりする根気、忍耐力です。問題解決に本気で取り組み、行動に移す力があるか、そして失敗しても立ち上がることができるか。これらは審査の基準となると同時に、ユースベンチャーになってからも大切にしている点だといいます。 人生最高の一冊を児童養護施設へ ユースベンチャー候補者のひとり、山内ゆなさんは、多くの人に児童養護施設について知ってもらい、そのうえで“人生で出会った最高の一冊”を児童養護施設に送る「JETBOOK作戦」を展開しています。児童養護施設とは、親がいない子どもや親から虐待を受けている子ども、あるいは経済的な理由で子どもを育てることができない家庭の子どもなど、2歳から18歳までの子どもが過ごす施設です。山内さんは2歳のときに入所し、18歳の現在も児童養護施設で生活されていて、そこで違和感を感じたことや行動したいと思ったことを、ユースベンチャラーとなって実現しようとしています。 15分のプレゼンテーションでは、山内さんはJETBOOK作戦の概要やそれを実施するに至った経緯について発表しました。彼女は、施設のことをたくさんの人に知ってもらうと同時に、施設の子どもたちに情報を得られる機会を届け、さらに施設の外にも頼れる大人がたくさんいることを伝えたいと話します。山内さんによると、児童養護施設のことを知らない人は多く、少年院と同種のものだと勘違いされることもあるそうです。また、そこに住んでいることで、友人から「親がいないのに聞いてごめんね」と言われたり、住んでいる子どもたちにとっては当たり前の生活が、外からは重たいものに感じられたりすることに違和感を感じているといいます。 「小中学校のときは地域の学校に通っていたので、近くに施設の子がいるのが当たり前だと思い、周囲の反応も気になりませんでした。しかし自転車で少し距離が離れた高校に通うようになり、友達に児童養護施設に住んでいると言った時に、“親いないの?大変だね、頑張ってね”などと言われ、空気が重くなり、施設に住んでいることを言ってはいけないのかなという気持ちになりました。それを施設内で話すと、周りの子たちも同じように感じていて、施設の中外で大きなギャップがあると感じました」と話す山内さん。 そこで山内さんは、施設の中外の意識のギャップを埋めたいと考えるようになりました。 また、児童養護施設ではネット環境が整っていないところが多く、情報を得る機会が限られることから、山内さんは施設の子どもたちが情報を得られる機会を増やしたいと考えています。施設にネット環境が整わないひとつの理由は、子どもたちの個人情報を守るため。子どもたちが施設に入る理由の6-7割は親からの虐待で、親から身を隠さないといけない子どもたちが多くいます。そうした背景から個人情報や安全を確保する必要があり、それがネット環境の整備の足かせになっているようです。 「私自身、高校でバイトをしてケータイを買うまで、ネットに触れる機会はありませんでした。学校では、知っている情報量の違いから友人の話についていけないことが多かったです。それをどうにかしたくて、施設の子どもたちに情報を届けることができないかなと考えるようになりました。そんな折、年下の子から本を読みたいから教科書を貸してほしいと頼まれたのです。それが衝撃で、施設に本を増やしたいと思うようになりました。そこでツイッターで呟いたところ、20人くらいから本ならあげるよと言われ、自分でも調べてみると図書館では定期的に本を廃棄していることがわかり、それを寄付としていただくなど、私にも本を集めることはできるのではないかと考えるようになったのです」 またスマホでSNSを通じて施設外の人たちと交流するようになり、外部にも頼れる大人がいることを施設の子どもたちに伝えたい気持ちが芽生えたそうです。 「自分自身、ツイッターを通じてたくさんの大人と関わり、しかも継続的に関わってくれる人がたくさんいることに気づきました。児童養護施設では職員の方の離職率が高かったり、施設間の異動が定期的に行われたりと入れ替えが多いこともあり、大人を信じることが難しく、そもそも人に頼ろうとしない子どもたちもたくさんいると感じています。そこでJETBOOK作戦で、一人に一冊献本してもらい、その結果、施設の本棚に100冊の本が並ぶことになれば、子どもたちは100人の方が児童養護施設のことを知ってくれ、応援してくれていることがわかり、温かいメッセージになるのではないかと考えました」 山内さんは、JETBOOK作戦の第一弾を2020年12月から1月に展開。約320人に協力してもらい、320人の“人生に最高の一冊”を、2つの施設に送りました。さらに2021年5月には、100の施設に100冊を送る、1万冊規模のプロジェクトを計画しているそうです。 また、児童養護施設では新しいことを体験する機会が少ないため、協力者や企業に協力してもらい、ワークショップのような様々な体験ができる機会を作りたいと言います。そうした体験の場を通じて、施設の子どもが100冊の本から選んだ自分の好きな一冊を、他の施設の子と交換して施設間で本を循環させたり、子どもたちが施設外の大人と関われたりする機会を作りたいといいます。さらに子どもたちが18歳になり施設を出た後のケアについても改善の余地を感じていて、ボランティア団体がたくさんあるにもかかわらず、施設の子どもたちにケアが届いていない現状を、JETBOOK作戦や体験の機会を通じて改善することに意欲を燃やします。 山内さんは、次のように話し、プレゼンテーションを締めくくりました。 「児童養護施設のことを多くの方に知ってもらい、子どもたちが抵抗なく施設に住んでいることを言えるような社会や、社会的養護下にいる子どもたちを社会全体で育てていけるような仕組みづくりができたらいいなと思っています」 プレゼンテーションが終わると、質疑応答が行われました。 ガントス氏 アフターケアをする団体がたくさんあるにもかかわらず、ケアが子供に届いていないとおっしゃっていましたが、なぜたくさんあるのに子どもにケアが届いていないのか教えていただけますか? 「児童養護施設は閉鎖的なところが多いため、外部のボランティアを受けいれていないことがあります。子どもたちは18歳で施設を出ることになりますが、支援してくれる団体があっても、出所してすぐに彼らに頼れるかというとそうではないと思うのです。人間関係を構築するには、施設にいるうちから面識があり、近い関係になっていないと難しいと思います。私も18歳なのでもうすぐ施設を出ることになりますが、施設の児童としてボランティア団体の方と話をしたことはありませんでした。そこでワークショップなどでアフターケア団体にも協力してもらい、イベントなどを通じて顔見知りになれたらいいなと思っています」 佐藤氏 JETBOOK作戦で次に1万冊のチャレンジをされるとのことですが、その先に描かれている目標があれば教えてください。 「児童養護施設は全国に約600箇所あり、約27,000人の子どもたちが暮らしています。その全部の施設や、そのほかにも本を必要としている施設に本を届けたいと思っています。また施設間で本を循環させ、施設間の子どものつながりが増えるといいなと思っています」 佐藤氏 施設間のつながりを増やすために、ハードルになりそうなものはなんですか? またそのハードルに対してどのようにチャレンジしていくつもりですか? 「閉鎖的な施設が多いなかで、他の施設と一緒にイベントに出るとなると承諾を得るのが難しいと思っています。JETBOOK作戦の第一弾をやった時も、現場の職員の方には反対されました。そこで施設長に2週間にわたり毎日JETBOOK作戦の話をし、ようやく許可をもらえました。ひとつの方法がダメでも他に道があると思いますので、アプローチ方法を変えることで子どもたちがワクワクできるような体験を届けられたらいいなと思っています」 寶教授 第一弾をやった時の反響はどうでしたか? 「子どもたちの反響としては、本を通じて会話が増えたと思っています。一緒に読んだり、感想を伝えあう姿、『ミッケ!』や『ウォーリーを探せ』などの本を小学生同士が一緒に楽しむなど、子どもたち同士や職員との会話が増えたので、そういうことも外に発信していけたらと思っています」 このように質疑応答が繰り広げられ、いよいよ結果発表へ。パネリストによる協議の結果、山内さんは見事アショカ・ユースベンチャラーとして認定されました。認定されると活動のための支援が受けられ、またユースベンチャー同士で情報交換する機会が得られます。 最後に、結果発表を行った佐藤氏から山内さんに激励の言葉が贈られました。 「個人的な意見ですが、社会に対して自分の意見をぶつけようとすると、話されていたように前例がないとか、相手なりの良かれと思った正義によって阻まれてしまうことが多々あると思います。それに対しご自身で試行錯誤しながら、違うアクションでアプローチするような場面は、これからもたくさん出てくると思います。でも山内さんならその壁のひとつひとつを、熱い思いで乗り越えられるのではないかと思いました。引き続き、頑張ってください」 また寶教授からは次の言葉が贈られました。 「2歳の時から育った環境のなかで、こういうことをやりたいという、まさに内発的な動機をお持ちであることと、反対があっても挫けない行動力があり、発想も豊かだと思います。活動により施設内でのコミュニケーションだけでなく、施設間の交流を推進させ、地域に貢献することも考えている。住んでいる地域だけではなく、活動の幅がさらに広がる可能性を感じました」 ガントス氏は次のようにコメントしました。 「施設で普通に育って卒業する。何もしないでその過程を辿っていくことも当たり前にあると思います。しかしそこで問題を提起して、反対されてもなんとかして解決していく。そのパワフルな想いは貴重なものだと思います。頑張ってください」 パネリストの方々から高い評価を得た山内さん。彼女の活動内容やプレゼンテーションは、多くの方々の心を動かしたようです。審議会をパスすることは彼女とってゴールではなく、ひとつの通過点に過ぎないと思います。山内さんの、これからの活躍に期待しています。 アショカジャパンでは、2012年に第1回目のパネル審査会の実施以降、これまで43回の審査をパスした若者は110チーム以上。これからも頻繁にパネル審査会を実施し、人材の育成に力を注いでいくとのことです。次はどのようなユースベンチャラーが誕生し、社会に影響を与えていくのか。アショカジャパンの取り組みとユースベンチャラーの活躍に期待したいと思います。 Ashoka Japanのオフィシャルwebサイト https://www.ashoka.org/ja-jp/country/japan フィアットが大切にしているシェアの気持ち「Share with FIAT」 Text/ Takeo Somiya(Fresno Co., Ltd.) […]
低所得国の子どもたちに教育のギフト(贈り物)を。ルーム・トゥ・リードの活動とその思いを聞く。
#Room to Read#Share with FIAT#ルーム・トゥ・リード・ジャパンRoom to Read(ルーム・トゥ・リード)は、アジアやアフリカなど16カ国で子どもたちに教育支援を行なっている国際NGO。支援先の国々では、今なお貧困や文化的背景から、教育環境が行き届いておらず、読み書きができない子どもが多くいるほか、男女間の教育格差が存在するといいます。今回は、ルーム・トゥ・リード日本法人の事務局長、松丸佳穂さんに、低所得国の教育を取り巻く問題や、その解決に取り組む活動についてうかがいます。 日本にいると初等教育で字を習うのは当然のことのように考えてしまいがちですが、世界に目を向けると、読み書きができない方というのはどれ位いるのでしょうか。 「世界では読み書きができない非識字人口は10億人近くいて、成人でも7億5000万人以上が基本的な読み書きができないというデータがあります。さらにその3分の2は女性や女の子で、低所得国では4人に1人の子どもが読み書きができません」 かなりの数ですね。ルーム・トゥ・リードでは、どのように教育支援を行なっているのでしょうか? 「ルーム・トゥ・リードは、質の高い教育によってすべての子どもたちが自分の可能性を最大限に発揮し、地域社会や世界に貢献できる世界を目指しています。教育における識字と男女平等に焦点を当てることで、低所得層のコミュニティに住む何百万人もの子どもたちの生活を変えようとしています。私たちの支援活動は、大きく分けて2つあります。ひとつは、初等教育の子どもたちの識字能力と読書習慣を育成する “識字教育プログラム”です。先進国では、義務教育の過程を通じて、自然と識字能力を身につけていきますが、私たちが支援しているアジアやアフリカの低所得国では、現地の言語で書かれた本や教材がほとんどなかったり、そもそも学校に図書室がなかったり、先進国では当たり前に存在するものが圧倒的に不足しているのです。そこでルーム・トゥ・リードでは、現地語による本や教材の開発から図書室の開設、教師や司書のトレーニングなど、子どもたちが生涯自立した読書家になれるよう読み書き学習に必要な支援活動を行なっています。もうひとつは、“女子教育プログラム”と呼ばれるもので、少女たちが学業における成功と、卒業後の豊かな人生のための必要なライフスキルを身につけ、高校を卒業できるように支援しています。なぜ支援対象が中学・高校の女の子かというと、小学校のうちは男女間で就学率の差というのはあまりないのですが、中学、高校と上がるに連れ、女の子の進学率は下がり、中退してしまう子も多いのです。その理由はいくつもあります。貧困から学校の代わりに、家事労働に従事する女の子も多いです。また、女の子に教育はいらないという文化的偏見やジェンダー差別、また、安全性への懸念もあります。中学や高校が近くになくて、家から5km、10kmと離れていることもよくあります。舗装されていない道を1時間や2時間歩いての通学は、体への負担だけではなく、身の危険にも晒されるますから、親が行かせたがらないこともあります。さらに学校に通えても、女性の教員が少なかったり、男女別のお手洗いがなかったり、女の子にとって学校が安心できる場所ではないという理由もあります。また、世界では結婚や出産を18歳未満で経験する女の子がいます。“児童婚”と呼ばれていますが、これも女の子が学校に通うことができない大きな要因のひとつになっています。このように、本人に学習意欲があったとしても、様々な理由から学校に行けなくなってしまうのです」 セキュリティやインフラ面、さらに社会環境が弊害になることが多々あるのですね。そのような問題に対して、どのようにアプローチしているのでしょうか? 「ルーム・トゥ・リードの女子教育プログラムは、少女が学校に長くとどまり、物事を判断する基準やプロセスを持ち、日常にある課題に対し自分で対処する自信を育み、意思決定ができるスキルを身に着けたうえで、高校を卒業ができるように設計しています。その一つとして、中学から高校までの間に、40から60のライフスキル教育、文字通り“生きるための力”を学ぶ授業を提供しています。 批判的思考や自尊心、自立心は、日々の課題に対処し、十分な情報に基づいた意思決定に役立ちます。こうしたスキルを身につけ、それを日常生活にどう役立てるかを学習した女の子は、性差別に対処する方法から勉強のための時間をどう作るかまで、今後直面するかもしれない障害を克服し、卒業後の生活に備えることができます。 最初は、自分の意思で物事を判断する習慣がなかった子どもたちは、“私って何?”“好き・嫌いって?”というところからスタートします。最初は、自分が“嫌”という気持ちをどう表現したらいいかも分からないのです。高校生になると、キャリアや試験対策、性的権利や安全性、ディベートやコミュニケーションなどを学びます。 ライフスキル教育に加えて、女の子にメンターとなる女性のメンターも重要です。私たちはソーシャルモビライザーと呼ぶ、地域社会における強力なロールモデルとなる女性を派遣しています。少女達が生活の中で直面する可能性のある問題に対処するために、メンタリングのセッションを実施しています。セッションは、グループ単位、あるいは個人に対しても行われます。少女にアドバイスを与えたり、心理的なサポートを提供すると同時に、教師や家族と緊密に協力して、課題に対処していきます。自分の悩みや思っていることを相談できる人が身近にいるというのはとても重要で、親にも言えないことをメンターに相談し、問題を一緒に乗り越えていくのです。いつも見守ってくれる人がいて、学校に行けば同じように頑張っている仲間もいる環境というのが、女の子たちの大きなモチベーションになっているのです」 コロナ禍で学校に戻れないリスクも 見守ってくれる人がいれば心強いのは誰でも同じですね。ところでコロナ禍の影響はいかがでしょうか? 「コロナの影響は計り知れないほど大きいなか、子ども達が教育現場から取り残されることがないよう、できることから迅速に対応をしてきた年でした。コロナに関するニュースは毎日報道されていますが、低所得国の状況はほとんど伝えられていません。パンデミックや自然災害が起こると、大きな影響を受けるのが、社会的に立場が弱い女性や子どもたちです。教育面でいうと、日本を含めて先進国では多くの学校でオンライン学習に移行しましたが、ネパールやタンザニアなど、ルーム・トゥ・リードが支援を行っている国々では、インターネットが普及しておらず、すべてをオンライン学習に移行することができません。ただでさえ貧しいなかでコロナが直撃し、両親が失職し、早すぎる結婚やジェンダーに基づく暴力、人身取引、中途退学なども報告されています。 低所得層のコミュニティにいる何百万人もの子どもたちにとって、コロナによる学校閉鎖は、一時的な学びの“中断”ではなく、学びの“消失”を意味します。読書の消失、学びの消失、そして自らの人生や所属するコミュニティに明るい変化をもたらすという夢の消失です。 ルーム・トゥ・リードの遠隔学習プログラムは、インターネットに依存していません。ラジオ、テレビ放送を通じての授業提供、電話、テキストメッセージを通じてのフォローアップ、他団体と協力して各家庭への印刷教材の配布など、子どもや保護者たちが最も利用しやすいチャンネルを通じて、支援を行っています。また、インターネットにアクセルできる人達には、デジタル学習プラットフォーム「リテラシークラウド(英語)」を無償で提供しています。読解レベルと言語で分類された絵本21か国語1000タイトル以上がアップロードされた豊富なオンラインライブラリに加え、教師、児童書作家、国際的な出版界のメンバー、政府向けの読み聞かせビデオや専門的な開発リソースが掲載されています。 また、女の子たちに対して、職員は電話でメンタリングセッションを行い、危機を乗り越えるべく精神的に支え、自宅で学業を続けるためのサポートを行っています。また、安全で健康的な生活を送れるよう情報提供し、学校が再開した際にスムーズに戻ることができるよう課題解決を一緒に行うなど、遠隔でサポートを行っています」 教育環境がより深刻になっているなかで、ラジオやテレビで支援を行なうなど、ルーム・トゥ・リードの活動の規模やスピーディな対応力には目を見張るものがありますが、スタッフの方はグローバルでは何名ぐらいいらっしゃるのでしょうか? 「ルーム・トゥ・リードの職員は、グローバル全体で約1600人、うち9割はプログラムを実施している支援国に在籍しています。ルーム・トゥ・リードの活動資金は、主に皆さまからいただく寄付金を使わせていただいていますが、間接費を徹底的におさえ、寄付の透明性にこだわり、組織や活動をビジネスと同じようにスピード感をもって運営しているのが特徴です。米国には慈善団体を評価する“チャリティナビゲーター”という第三者機関があり、財務の健全性、説明責任、透明性を重視しており、その評価基準はとても厳しいですが、ルーム・トゥ・リードは最高評価である4つ星を獲得しています。私達はお預かりした寄付の85.9%を、支援国における教育プログラムの実行のために投入していますが、寄付金が健全に運用され、世界を変革していくためのミッションが着実に達成されているということを裏付けるものです。また、昨年は設立から20周年のタイミングでしたが、現在までに1800万人以上の子ども達へのサポートを実現しています。ただ、最初にも申し上げましたが、世界では読み書きができない非識字人口はまだ10億人近くいて、低所得国では4人に1人の子どもが読み書きができません。私達は、2025年までに4000万人の子ども達に教育を届けるという新たな目標を掲げています」 次に日本での活動についてお聞きしたいのですが、主な活動は支援者を集めることでしょうか? 「そうですね。日本ではルーム・トゥ・リードの活動を知っていただくための啓発活動と資金調達活動を行っています。もちろん経費も厳しく見ていて、現在、日本にはオフィスは2拠点ありますが、企業や個人から無償で提供いただいます。また、日本には職員は私一人しかおりませんが、多くの企業のプロボノや個人のボランティアサポーターの皆さんに、資金調達からイベントサポート、翻訳やウェブサイトのリニュアル、SNS、事務局のサポートに至るまで、日々の活動を一緒に支えていただいています。フィアットさんにも秋に開催したバーチャルガラではイベントスポンサーとして協賛していただきました。 コロナのようなことがあると、自分達の生活も先が見えなくなってしまい、報道でもルーム・トゥ・リードの活動地域のニュースはほとんど流れませんので、どうしても内向きになってしまうことが多いと思います。ただ、少し外に目を向けていただいて、学校閉鎖によって、二度と教育現場に戻ってこられないかもしれない子ども達がいることにも思いを寄せていただけたら嬉しく思います。もちろん、日本にもコロナ禍で浮き彫りになった課題はたくさんあり、そのサポートをしている団体もたくさんあります。自分が関心を持つ課題に対して、自分ができることはないか、アクションを起こすことが大切だと思います。そこはまさに、フィアットが提唱している“Share with FIAT”の精神だと思います。ルーム・トゥ・リードが提供している女子教育プログラムもそうですが、私たちは、誰でもひとりでは絶望的な気持ちになってしまうことでも、周りの支えがあることによって勇気が得られます。個人個人が自分が持っているものを少しずつShareすることで、世界は大きく変わると信じています」 松丸さんは日本法人の立ち上げからずっとやられていて、こういう組織にしていきたいという思いはありますか。 「私は自分が前に出て、組織の顔となって引っ張っていくタイプではありません。ただ、ルーム・トゥ・リードのビジョンに共感していただいて、リーダーシップを持った素晴らしい人を巻き込んでコミュニティやチームを作ることを得意としています。毎年クリスマスの時期に、寄付キャンペーンAction for Educationを開催しているのですが、昨年12月はコロナ禍にいる子ども達に教育のクリスマスプレゼントを届けようと呼びかけました。日本全国から、そして海外からもご支援をいただき、おかげさまで目標を大幅に達成し4,144名の子ども達をサポートすることができました。 資金調達に際しては、32名もの多才なサポーターたちが自らチャレンジャーとなって、自身の好きなこと、得意なことを生かして、続々とユニークなファンドレイズのプロジェクトを立ち上げてくださり、寄付を募ってくださいました。お金に余裕のある方は寄付をしてくださったり、スキルがある方はご自身のスキルと時間を提供してくださったり、関わり方は様々です。一人ひとりが自分ができることをアクションしてムーブメントにしていくことがルーム・トゥ・リードらしさだと思っています。結果としてプロフェッショナルな方が集まってくださり、お一人おひとりが機会を生かして行動を起こしてくださったおかげで、子ども達、家族、コミュニティの将来に大きな変化が生まれているのです。」 最後に2021年の抱負を教えていただけますか。 「2020年はコロナ禍で春に予定していた資金調達を目的としたガラパーティや数々のイベントがすべてキャンセルになり、前半は資金調達の点では非常に苦しい状況となりました。ただ、秋に、これまで手がけたことがなかったバーチャルでの資金調達イベントを何度か開催し、おかげさまで多くのご支援をいただくことができました。バーチャルの利点としては、首都圏以外の支援者の方々にも多数ご参加いただけて、また、海外からも多くのゲストスピーカーがご参加くださいました。さらに、タイムリーに参加できない方には録画を共有することもできました。今年も、ルーム・トゥ・リードの活動を知っていただきたいので、バーチャルという新たな機会も生かしながら、状況を見ながらですが、リアルイベントなどとハイブリッドの組み合わせで進めていけたらと思っています!」 今日はお忙しいなか、ありがとうございました。 ルーム・トゥ・リード公式サイト ルーム・トゥ・リードのSNS(Facebook・Twitter・Instagram) フィアットが大切にしているシェアの気持ち「Share […]
災害の緊急支援から復興まで。“早く、深く”被災地を支援。ピースウィンズ・ジャパンの活動とその思いを聞く。
#Peace Winds Japan#Share with FIAT#ピースウィンズ・ジャパンPeace Winds Japan(ピースウィンズ・ジャパン)は、自然災害や紛争などにより、生活の危機にさらされた人々の支援や、殺処分の対象となった犬の保護など、さまざまな社会問題に取り組む特定非営利活動法人。1996年の設立以来、「必要な人々に必要な支援を」をモットーに、これまでに33の国と地域で支援活動を展開しています。今回はその第一線で活躍されているピースウィンズ・ジャパンの国内事業部次長の橋本笙子さん、国内事業部の西城幸江さん、コミュニケーション部の櫻井綾子さんにご登場いただき、それぞれの活動やその裏側の話をうかがいました。 まずピースウィンズ・ジャパンの活動で驚くのは、その活動規模の大きさ。災害支援では国内外と広範に展開し、被災直後の緊急支援から復興支援までを行っています。緊急支援については、ヘリコプターまでを配備し、緊急出動に備えています。最近では令和2年7月に熊本県と鹿児島県に大雨特別警報が発令された際に、医師や看護師、レスキュー隊など約30名と救助犬、ヘリ2機などからなる支援チームを現地に派遣し、河川が氾濫した球磨川川周辺の被災地支援を行いました。 また、新型コロナウイルス感染症への対応では、1月末時点で中国にスタッフを派遣し、国内に備蓄されていた医療資器材やマスク50万枚以上を武漢や上海などに届けたことに始まり、1-4月には国内の約1,300の医療・福祉・児童施設にマスク140万枚を配布。さらに長崎に停泊中のイタリア籍クルーズ船コスタ・アトランチカでコロナ感染が拡大した際には、長崎県からの要請を受け、医師・看護師を含むチームを現地に派遣しています。表立って報道されないことも多いですが様々な災害の現場でピースウィンズ・ジャパンの方々が活躍しています。 活動範囲の広さもさることながら、緊急支援に始まり、現地の復興・開発まで、長期に渡り、支援の手を差し伸べているのも、特筆したいポイント。とかく世間の目は次々に起こる新しい災害の方に行きがちですが、被災地の復旧・復興には相当な時間を要することもあります。その主たるものが東日本大震災。ピースウィンズ・ジャパンでは、緊急支援に始まり、今なお地域の復興支援を続けています。例えば宮城県南三陸町に地域の方々が交流できるコミュニティスペース「晴谷驛(ハレバレー)」を設置し、かごづくりなどの活動を通じて、地域の方が趣味ややりがいを見つけたり、そうした活動を通じて他の参加者の方と交流したりして心が晴れやかになるような環境づくりを行っています。なおフィアットもピースウィンズ・ジャパンの東北支援プロジェクトをサポートしています。 こうして様々な支援活動を“早く”、“深く”実行されているピースウィンズ・ジャパン。そうした最前線の裏側では人々がどのように動いているのか、うかがっていきます。 災害が起きたとき、現地に素早く救援チームを派遣されていますが、どの段階で支援を開始するのでしょうか? 橋本さん ピースウィンズ・ジャパンでは、関係団体と空飛ぶ捜索医療団「ARROWS(アローズ)」というプロジェクトを編成しています。空飛ぶ捜索医療団のメンバーたちは常時ネットワークで繋がっていて、災害が発生すると一斉に情報を共有します。被災規模が大きく、被災者がいる場合には、直ちに医師や災害救助犬など医療を中心としたレスキュー隊を派遣します。また台風の場合では、ある程度事前に予想ができますので災害接近の48-24時間ほど前からスタンバイし、現地の災害対策本部と連携して災害の状況を確認し、救援活動を開始します。災害の規模にもよりますが、初期の1週間から2週間くらいまではレスキュー隊の派遣が活動の中心となり、並行してスタッフを派遣し避難所の運営や物資支援を進めていきます。 災害では、時間の経過と共に活動内容が変化すると思いますが、その時々の状況に応じて支援の内容を変えていくのですか? 橋本さん そうです。緊急支援は子育てと同じで、災害の発生直後は0から100まで面倒を見るつもりで従事し、時間が経つにつれ、少しずつ手を離していきます。場合によっては、辛くても、被災された方々の背中を押してあげることも必要だと思っています。被災地の自立のために少しずつ背中を押しながら、我々は去っていかなければなりません。とはいえ、自助・共助・公助といっても、例えば高齢者の多い被災地では、自助や共助には限界がありますので、手を差し伸べることが必要だと思っています。 プロジェクトの終わりはどのように判断するのですか? 橋本さん 終わりの判断はもっとも難しいところですが、被災された方が元の生活を取り戻すために、軌道に乗るところまでは後押しを続けたいと思っています。2018年の西日本豪雨の支援はまだ続けていますし、東日本大震災の東北支援も続いています。海外でも紛争地域の現場などでは終わりが見えないことが多く、長いところでは10年以上活動を続けているところもあります。 スタッフの方々は、本当に立派なことをされていて敬服しますが、いち個人としての生活や人生設計もあるかと思います。そのあたりは両立できていらっしゃるのでしょうか。 橋本さん この業界は女性が多いので、結婚や出産などライフステージにより色々な転機があります。この仕事に就いているからできない、という職場であってはいけないと思っています。個人の生活も守られながら仕事ができる環境づくりは大切だと思っています。 西城さん 自分たちの心と体が健康でないと、人の支援を続けるのは難しいというのが根底にあると思います。緊急の状況で行く10日間と、切迫した状況が過ぎた後の10日間では被災者の気持ちはまったく違います。やはりある程度、大変さの波はありますね。 橋本さん 東日本大震災に対応しているときのことですが、震災から1ヶ月後の4月頃に自分が壊れていくのがわかりました。私自身、心が崩れていくのを感じたのです。幸いにも自分自身でわかったので軌道修正ができたのですが、当時は数々の修羅場をくぐり抜けてきた国際協力の団体のスタッフでさえ、精神的にバタバタと倒れていき、1年や2年復帰できないほどのダメージを負った人もいました。海外であれだけの経験を積んできたのにどうしたのだろうと思いましたが、その時思ったのは、海外の現場への対応は、当事者ではなかったということです。一方、東日本大震災では災害が当事者のこととして重くのしかかってくる。目の前で起こっていることや現地で聞く声がストレートに体に吸収されていきます。やることが目の前に無限にあり、やってもやっても不十分という状況の中で無力感を感じて、メンタルを崩していく人が多いと感じました。 そのようなときはどうするのですか? 橋本さん 私たちの組織の中には労働基準法で定められている範囲でメンタルを含めたケアをチームもありますが、極限の状況下ではそうした人たちのお世話になるというよりは、同じ職場のスタッフ同士のコミュニケーションだったり、仲間との信頼関係だったりが重要だと感じています。私は本部にいて、現場ではプロジェクトリーダーがひとりで活動することも多いのですが、被災者に対してだけでなく、現地のスタッフにも、“あなたは1人ではない”ということが感じることができるように、支え安心させてあげることが必要だと思っています。 西城さん 常に予算に余剰があるわけではありませんから、現場も限られた中で人員配置をしていかなければなりません。現場では災害に対する無力感と隣り合わせのなか、あれもこれもやらなければならなくなる。タフじゃないとやれないですし、家族もある程度タフじゃないと厳しいと感じるかもしれません。 先ほど予算のお話が出ましたが、活動資金は政府の援助がない場合は、企業や個人の方からの寄付金で成り立つものだと思います。櫻井さんは資金を集める側のお仕事を担当されていらっしゃいますが、具体的にどのような活動をされているか教えていただけますか? 櫻井さん 現場での支援活動が表の部分だとすると、私がいるのは裏側の部分。緊急事態が発生し、救援チームが出動するぞとなった時に、裏側ではその活動資金をどう集めるか、という動きが起こります。広報チームが寄付を集めるための広報活動を行い、私の属する支援者サービスチームは、支援者からの問合せに対する準備を行います。 寄付金を集めてプロジェクトを回す。大変なお仕事ですね。 櫻井さん […]
自分らしさが選択できる社会のために。I LADY.の活動とその思いを聞く。
#Share with FIATI LADY自分らしい人生を、自分で決められるように I LADY.は、女性が心身ともに“健康”に生きられる社会を目指す、ジョイセフによるプロジェクト。健康といっても色々な健康があるけれど、I LADY.が活動の中心としているのは、性と生殖に関する健康。日本は医学が進んでいる先進国ではあるけれど、「性」の問題についていえば、それを取り巻く社会環境や人々の意識には、“遅れている?”と感じる部分も。その背景には、性はデリケートな問題なのでメディアで取り上げられることが少なく、社会の関心が向きづらい事情もあるのでしょう。そこで女性のいのちと健康を守ることを掲げている国際協力NGOのジョイセフが立ち上がり、I LADY.という活動を通じて、性や生殖面における女性の健康や権利にフォーカスしているというわけです。今回はそのI LADY.をけん引するジョイセフの小野美智代さんに、お話をうかがいます。 日本では、10代の中絶より40代の中絶の方が多い。 「性と生殖」の健康というのがあまりピンと来なかったので、具体的にどういう問題があるのか聞いてみました。すると、出てきたのがこの例え。あまり報道されないことですが、40代の中絶は10代より多いそうです。どういうことかうかがいました。 「中絶というと若い子たちという印象が強いと思います。わたしも6年ほど前に臨床の現場で人工妊娠中絶を施す産婦人科医からこの話を聞いたときは驚きました。40代というと不妊治療の話は聞きますが、中絶の報道はあまりされていませんね。中絶の理由を聞くと、わたしはてっきり婚外交渉とかかと思ったら、実際には多くが夫の子。たとえば長男長女が大学生になっていて、もう恥ずかしくて産めないとか、世間体があるとか、経済的な理由、子どもが20歳まで現役で働いて養う自信がない……など。産めないならなぜ避妊しなかったのか?と聞くと、夫がしてくれなかったという答えが返って来ることが多いようです。もちろん、妊娠は女性と男性の両方に起因するものだけれど、女性は自分のことなのに人任せにしてしまう。I LADY.ではこうした問題に着目し、自分の体のことは自分で守るという判断や行動を広めようという活動を行なっています。こうした概念を表したセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR=性と生殖に関する健康と権利)という言葉がありますが、I LADY.の活動の軸はまさにこれにあたります。わたしたちは、Love Yourself(=自分を大切にすること)。Act Yourself(=自分から行動すること)。Decide Yourself(=自分らしい人生を、自分で決められること)。というキーメッセージを発信し、これを実践できる人を増やしたいと思っています。SRHRの知識や意識を持つことは、自分の人生をよりよく生きる力になるライフスキルだと思っていまして、その普及を目指しています」。 自分に関わる問題ではあっても、人に委ねてしまったり、社会の空気に飲まれてしまったり、 “自分”を周りに合わせてしまう人が多いなか、そこに自分の意思に向き合って自分で選んで決断しようと。自分をもっと大切にしようよと。そういう意識を広めているわけですね。 「日本では、世間の空気に流されることや、自分を出さないことやNOと言わないことが美徳とされているところがあると思います。遠慮という言葉もあります。それ自体を否定はしませんが、時には自分の権利を主張して、流されないようにすることも必要だと思います。まずは気持ちの上で、自分自身を大事にするという意識を大切にしていただきたいですね」。 そうした考えを広めるI LADY.の活動にとって、理想とする社会とはどのようなものでしょうか? 「自分の人生は自分で決める。そういう生き方をしている人を、わたしたちは“I LADY.に生きている”、”I LADY.な人”と呼んでいますが、いまI LADY.に生きるアクティビストは、著名人を含めて155人位います。自分なりの人生を実践している人が100人いるとすれば、その生き方は100通りあるということです。若者たちの自殺が多い日本。先進国で若者の自殺が多い国は珍しいのに、わが国では大人になりたくない若者が年々増えている。そうした時代だからこそ、わたしたちが理想とするのは、I LADY.に生きる人たちが溢れる社会。自分のライフスキルが備わった人たちが増えていくことが理想だと思います。自らの生き方を自分で決め、イキイキとしている方が増えれば、そこに触発されて、自分らしさ=自分の個性に向き合う人が増えていく。他人とは違う自分のことを肯定できるようになって、自己肯定感が高まれば、自然と元気になって生きることが楽しくなる。他者の個性を認め、尊重することが当たり前になると思います。多様性やダイバーシティという言葉をあちこちで聞くようになった今、真の意味でお互いを認め合い、元気を交換し合えるような輪が広まっていくことにも繋がると思うんです」。 最近のI LADY.の取り組みについて教えてください。 「I LADY.に生きているアクティビストを増やして、その方々を皆さまに紹介していくというのが私たちのひとつのミッションです。年を通じてジョイセフが大切にしている記念日がふたつあり、ひとつは3月の国際女性デー、もうひとつは10月の国際ガールズデーです。そこでイベントを開催しアクティビストに登壇してもらい、啓発活動を行なっています。また、ウェブサイトでインタビュー記事を発信したり、【パジャマでおしゃべり】というYouTube企画で対談したりして、彼らがどのようにI LADY.に生きてきたかを発信しています。直近では、9月26日の“世界避妊デー”に、参加無料のオンラインイベントを実施し、9月28日には安全な中絶/流産を選ぶ権利に目を向ける“インターナショナル・セーフ・アボーションデー”というのがあるのですが、それに合わせてアクティビストたちと安全な中絶について考える機会を設定しています。最近は新型コロナウウイルスの影響で実施できないリアルイベントが多いので、オンラインの活動にも力を注いでいます」。 小野さんご自身がそうした活動を取り組まれるようになったきかっけについて教えていただけますか。 「わたしは旧家の初孫で、女の子として生まれてきて、親族にがっかりされたんです。母は男の子を産まなければというプレッシャーを感じていました。結局男の子は生まれず2人姉妹なのですが。でも親族皆が可愛がってくれ、差別されたというわけではなく寵愛を受けて育ちました。一方で、わたしは物心ついた頃から祖父から、うちの跡取りだから婿を取るんだぞと言われ続け、その陰で嫁である母には男の子を産んでくれと言っていたことがわかりました。なぜ男の子じゃなければいけないのか。まだ性差やジェンダーという言葉がわかっていなかった頃に、わたしにはそういう意識が芽生えたのだと思います。ジョイセフに来るきっかけもジェンダーやSRHRに興味があったからです。以前は大学の職員をしたのですが、アジアに旅行した時、カンボジアで出会った友達が2年後に出産で亡くなってしまったのです。当時、出産で亡くなるという理由がわからず質問したのですが、明確な答えは返ってきませんでした。日本では病院で出産するのが一般的ですが、当時カンボジアでは自宅で出産するのが当たり前で、彼女は3日間陣痛で苦しみ、お腹の子とともに亡くなってしまったんです。それで大学でカンボジアの出産事情を調べた時に、ジョイセフに出会いました。ジョイセフが国連人口基金の世界人口白書を日本語訳しており、そこでカンボジアや途上国では多くの女性が出産で亡くなっている現実を知ることになりました。またそれが女性の平均寿命を短くしていることも。そこからこの分野に関心を持ち、ジョイセフに入りたいと思うようになり、3年半後に募集があったので入ったのです」 気持ちいいことを人に伝える ジョイセフでは、世界に妊娠や出産で命を落とす女性がたくさんいるという現実に目を向け、「ホワイトリボンラン」というチャリティラン・イベントを国際女性デーに開催していますが、これは途上国で女性のいのちと健康を守る活動へのチャリティを行なうと同時に、日本の参加者の女性にも走るという機会を通じて健康を促進する活動だと思います。これもランニングを愛好されている小野さんご自身の体験から発展した活動なのですか? 「わたしが走ることになったのは、東日本大震災の時に出会ったある女性のひと言からでした。避難所で被災者の声をヒアリングし、困っていることがないか聞いて回っていた時に、67歳の女性からどこから来たの?と聞かれ、静岡県と伝えたら、静岡や中部地方は東海地震が起こると言われているけど、対策は取っているかと逆に聞かれたんです。その女性は津波で娘さんを亡くし、残された3人のお孫さんを育てていました。わたしは当時、37歳。亡くなられた娘さんと同い年だったんです。そんな偶然もあり、“あんた子供いるの?””と聞かれ、3歳の娘がいますと答えたら、何かあった時にその子を抱えて走れる、逃げられるくらいの体力をつけておきなさいと言われたんです。お嬢さんと3人の息子は、逃げている時に第二波が来て、7才の子は自力で屋根の上に登れた。5才の子も上がった。お母さんは2才の子を抱えていて7才の子に渡せた。でも自分の身体を上げることができず、体力がつきて第二波で流されてしまったんです。7才と5才の子供は、目の前でお母さんが流されていく姿を見ていたそうです。その話が衝撃的で……。今のわたしは娘を連れて逃げられないと思ったし、健康にも体力にも自信がない。もし明日地震がきたら自分も娘も助からないと本気で思いました。それでわたしはそのことを地元の友人に話し、一緒に運動することを始めたんです。週に1回のウォーキングから始まり、ジョギングをやるようになった。そうしたら明らかに運動する以前よりも健康になり、体力に自信もついて、風邪もひかなくなった。わたしでも変われたので、これを子育て中の母親たちに勧めたいと思い、HiPsというコミュニティを作りました。毎月、満月の日に集まって走って、参加費100円を被災地に寄付するのです。それをホワイトリボンランに移行したのは、わたしが二人目を出産して育休中のとき。国際女性デーが3月8日にあって、ちょうど満月ジョグの日でした。いつもやっている100円寄付を、ジョイセフを通じて途上国の女性を支援しようとtwitterやFacebookに投げかけたら、静岡だけでなく、それが全国に共感が生まれ連鎖した。自分が気持ちいいことを人に伝えたら、それが全国に広がった。いいことを共有するって、こういうことなんだって実感したのです」。 そのホワイトリボンランにはフィアットも出展し、写真を撮ってポストした参加者にミモザの花を配布したりしましたね。最後に今後の展望を教えていただけますか。 「フィアットにはすごくシンパシーを感じています。フィアットのお客さんって、自分のやりたいことを自分で選んでいる女性だと思いますが、ジョイセフのファン、支援者も同様で。ジョイセフは大きな国際組織でないのでそこまで知られていないと思うのですが、ファンの方は自分でこの小さな団体を選んで支援してくれているんです。女性がイキイキしている社会は、フィアットとジョイセフが共通して目指しているところなので、これからも連携して、一緒に活動できる機会を増やしたいです。一人ひとりがLove, Act, Decide yourselfするI […]
3月8日の国際女性デーとイタリアのミモザの日ってどんな日?楽しみ方も紹介
#500#500C#ciaoDonna#Mimosa#Share with FIAT#ミモザ#女性活動毎年3月8日は、国連が制定した「国際女性デー」です。そして、イタリアでは「ミモザの日」とも呼ばれています。この記事では、国際女性デーとミモザの日が何の日でどんな関連性があるのか、また、具体的な楽しみ方やイベントなどをご紹介します。 国際女性デーはニューヨークの女性労働者が参政権を求めてデモを行った日 国際女性デーは、1904年3月8日にアメリカのニューヨークの女性労働者が参政権を求めてデモを行った日です。このデモを受けて、1975年に国際女性デーが制定されました。現在は国連事務総長が加盟国に対して、女性が平等に社会参加できるような環境づくりを呼び掛ける日になっています。 国連だけでなく、途上国の女の子の支援プロジェクト「Because I am a girl 」などを実施している公益財団法人プラン・インターナショナル や民間企業などもイベントやシンポジウムを開催するなど、世界中で女性の社会参画を願った取り組みがなされる日なのです。 イタリアでは女性にミモザを贈る「ミモザの日」 女性の社会参画を願う日とされている3月8日の国際女性デーは、イタリアでは同時期にミモザの花が咲くことにちなんで、ミモザの日とも呼ばれています。3月あたりにはミモザの花が咲き乱れ、イタリアの街中の随所でミモザの花が飾られたり売られたりするようになるのだそうです。 このミモザの日には、男性が女性に敬意と感謝を込めて、ミモザの花を贈るのがならわし。パートナーだけではなく、母親や祖母、友人、仕事仲間など自分にとって大切な女性に贈るのだとか。女性たちは贈られたミモザを飾るだけでなく、仕事や家事、育児からつかの間離れて、お出かけや外食を楽しむのだといいます。 また、ミモザの花は「春を告げる花」としてイタリアだけでなく、ヨーロッパ全体で広く愛されています。例えば、フランスのマンドリュー・ラ・ナプールという街では、2月に「ミモザ祭り」が開催されるそうです。 ミモザはアカシアの総称で花言葉は「秘密の恋」 ミモザは、正式にはマメ科ネムノキ亜科アカシア属の総称で、和名は銀葉アカシアと言います。ヨーロッパで人気があるミモザは、実はもともとオーストラリアが原産で、国花にも指定されている花です。 ミモザの花言葉は「優雅、友情」で、黄色のミモザの花言葉は「秘密の恋」。花屋でミモザの切り花が買えるのは1~3月で、3月8日のミモザの日近辺は日本の花屋でも手軽に手に入れることができます。自分で手にいれても、イタリアの風習や花言葉を男性に教えて贈ってもらう、なんて楽しみ方もいいかもしれません。 リースやサラダでミモザの日を楽しもう ミモザは、花束として部屋に飾るだけでなく、リースにしても楽しめます。また、ミモザの彩りを再現したミモザサラダのつくり方も紹介するので、ぜひミモザの日を楽しんでみてください。 花束と麻紐を使うミモザリースのつくり方 ミモザリースは完成品を花屋で買える場合もありますが、花束と麻紐があれば簡単につくることもできます。 1.麻紐はミモザを適量で結べるくらいにカットして、ミモザの花の付け根で結びます。余った紐はカットし、茎の下のほうから生えている脇花もカットします。 2.茎を覆うように、カットした脇花を重ねて紐で結び、茎部分も紐で結んで固定します。 3.茎部分をアーチ状に曲げ、花がついた先端に被せるようにして輪をつくります。葉の位置やリース全体の形を確認しながら紐で結び、整えて完成です。 ミモザの花そっくりのミモザサラダのつくり方 ミモザの花を使用するわけではありませんが、ミモザの花に見た目がそっくりなサラダのつくり方を紹介します。簡単につくれるので、料理に自信がない方もぜひチャレンジしてみてください。 【材料】 ・ゆで卵 2個 ・ミニトマト 3個 ・ベビーリーフ 40g ・オリーブオイル 小さじ4 ・すりおろしニンニク 小さじ1/2 ・レモン汁 小さじ1/2 ・塩 ふたつまみ 【つくり方】 1.ミニトマトはヘタを取り除き、4等分に切る。 2.ゆで卵は白身と黄身に分けて、それぞれ粗めのザルに押し付けて裏ごしをする。 3.ボウルにAの調味料を入れて混ぜ合わせる。 4.器にベビーリーフ、ミニトマトを盛り付け、真ん中に裏ごししたゆで卵の白身と黄身をミモザの花に見えるように盛り付けます。最後にAのドレッシングをかけたら完成です。 ミモザにちなんだFIATの限定車のフェア開催 […]
女性の力を、より良い社会へ。国際女性デー記念企画
#ciaoDonna#Share with FIAT#ミモザ#女性活動3月8日は、国際女性デー。この時期、各地で女性の活躍に注目したさまざまなイベントが行われます。──自分の幸せだけでなく、みんなの幸せを求める時代をつくっていきたい──フィアットでは、そうした想いのもと、Share with FIATの支援活動のひとつとして、2011年より女性のエンパワーメントや教育等のための活動をサポート。今年も、3月2日(土)と3日(日)に開催されたチャリティランニング大会「ホワイトリボンラン2019」、そして3月14日(木)開催の「アジア女子大学 第10回ファンドレイジングイベント」に協賛しました。この2イベントの模様をレポートします。 同じ想いのもと、笑顔で走るホワイトリボンラン 今年で4回目の開催となるホワイトリボンラン。妊娠・出産・中絶で命を落とす女性が世界にたくさんいるという現実に目を向け、国際協力NGOジョイセフがそうした犠牲者をなくすことを目標に、チャリティランニング大会を実施。この取り組みに賛同したランナーが全国から集まり、支援の輪を広げました。 参加者は日本全国の38拠点で延べ2484人、個人で走る「どこでも誰でもバーチャルラン」を含む総参加者数は、3208人に達しました。3月3日(日)には、初めて大阪で女性だけで走るウイメンズランが実施され、大阪城公園・太陽の広場に200人近いランナーが集まり、ともに汗を流しました。なお、ホワイトリボンランの参加費の半分は、世界の女性たちの命を守るための活動に寄付されます。今年の支援先はケニアとザンビアの2ヶ国です。 ランニングが始まる前のオープニングセレモニーは、ジョイセフの小野美智代さんのあいさつに始まり、吉本新喜劇の宇都宮まきさん、ゲストランナーの山田花子さん、座長の酒井藍さんらがステージに上がり、曇り空を吹き飛ばすような元気なトークで会場を盛り上げてくれました。 また、FCAジャパンマーケティング本部長 ティツィアナ・アランプレセもランナーの女性たちにメッセージを発しました。「女性は強い。だけど、女性のエンパワーメントは女性が一人で達成できるものではありません。一緒になって女性の権利のために戦わなければいけないのです」そう述べたあと、会場の皆さまと大声で「CIAO DONNA!(チャオ・ドンナ)」と元気なエールを贈りました。 大勢の女性がSNSを通じて元気を発信 フィアットは今年もミモザの花を持って応援に駆けつけました。白い500C(チンクエチェント・シー)と、たくさんのミモザの木箱を展示したフィアットブース。#ホワイトリボンラン2019、#ciaoDonnaのハッシュタグによる写真投稿を通じて元気を発信した女性に、ミモザをプレゼントしました。 最後に大会主催者の公益財団法人ジョイセフからいただいたメッセージを紹介しましょう。 女性を支援する国際協力NGOジョイセフにとって、国際女性デーはもっとも大切な1日です。2016年からはこの日に近い週末にホワイトリボンランを開催しており、今年は初めてウイメンズランを大阪で実施しました。初参加の方々も多く、“走ることで女性の力になれる”ということを大勢の方と共有でき、うれしく思います。世界では、女性の命・健康に関する環境は厳しいと言わざるを得ない状況です。日本は世界をリードする最長寿国ですが、そこから支援を届けることはとても意義のあることだと考えます。ひとりでできることは限られていても、皆でつながれば、大きなムーブメントを起こせます。自分の人生は、自分で選ぶ。そんなあたりまえをすべての女性に届けるため、これからも“できるアクション”の輪を広めていければ、と思います。 アジアの優秀な女性を地域のリーダーへ 3月14日(木)、東京アメリカンクラブで「アジア女子大学 第10回ファンドレイジングイベント」が開催されました。地域のリーダーシップとなる人材の育成を掲げる同国際大学は、バングラディッシュ・チッタゴンにキャンパスを構え、優秀であるにもかかわらず、大学教育を受けることのできない南アジアや中東などの子女に、高等教育の機会を提供しています。学費は主に、支援者や協賛企業からの支援による奨学金でまかなわれています。 家族のなかで大学教育を受けるのは初めてという生徒が多く、また約10%はいわゆる難民出身者なのだそうです。彼女たちは初めて故郷を離れ、チッタゴンのキャンパスで学園生活を送ります。 アジア女子大学のニルマラ・ラオ副学長が、これまでの大学の10年の歩みを振り返りました。「アジア女子大学は2008年、金融危機による混乱の時期に設立され、去年設立10周年を迎えることができました。設立当時、学生は大きな不安とリスクを背負って集まってきました。初年度の生徒数は128人。彼女たちはネパールの山村地帯や、スリランカの紛争地域などからやってきました。大学では、地域社会において、共感力を持って変革を起こすリーダーの育成に努めますが、優秀な人材を輩出しても、就職できるという保証はありませんでした。そうした状況でスタートしたのです」と、設立時の状況について説明しました。しかしそうした懸念は杞憂だったと語ります。 「1期生から優秀な生徒が育ち、使命感を持って地域の発展に貢献し、後にオバマ財団からアジアの若きリーダーのひとりとして表彰された生徒もいます。そうした初期の学生に誘発され、生徒たちは毎年約25%のペースで増加。卒業生はこれまでに700名を超え、1-5期生の卒業生の85%が就職または進学しています。しかも卒業生はユネスコやオックスファムといった団体のほか、アクセンチュアやシェブロン、ロレアル、マリオットなど世界の名だたる企業に就職し、質の高い生活を手にしています。また25%を占める大学院に進学した生徒は、世界各国の教育機関で活躍し、地域に貢献しています」と卒業生たちが立派な進路へと進んでいることを紹介しました。 副学長は、続けます。「こうした活動を支えてくださっている支援者の方々の存在は大きな励みになりました。日本の支援グループは2008年の学校設立と同時に誕生し、学校の運営費用の38%は日本からの支援で成り立っています。この場をお借りして御礼申し上げます。また今後も教授陣やプログラムを拡大していき、学生数は現在の約4倍の3000人を目指します」と、野心的な目標を掲げました。そして「女性たちの大胆な夢の実現に向け、彼女たちを支え続けていきます」と述べ、スピーチを締めくくりました。 「自力で成功された女性50名」に選ばれた久能祐子さんが基調講演 また会場では、米S&R財団理事長兼CEOであり、ハルシオン創立者兼議長も務めていらっしゃる久能祐子さんが基調講演を行いました。彼女は日本出身の起業家で、現在はワシントンDCで活躍。『Fores』誌から、「アメリカで自力で成功を収めた女性50人」に選出されています。 久能さんは、その成功までの道のりを3つの章に分け、それぞれの時代の転機や、後の成功に結びつく因子を振り返って述べられました。第1章は、学生時代。3人兄弟の次女として生まれた久能さんは、教育に熱心なご両親のもとで、京都大学に進学。性別を分け隔てなくサポートしてくれたご両親のサポートと、子どもの頃「恥ずかしがり屋だった」ことを理由にコミュニケーションを取らなくて済むと思って進んだ理工学部を選んだその選択が、その後の人生を大きく変えたことを紹介しました。また当時、同学年の女子はわずか6人と理工系の女子学生数が少なかったことから、教授から女性の研究者が多くいる環境の米ニューヨークの大学への交換留学を提言されたそうです。そして「ニューヨークで素晴らしい経験を積むことができた」と語られています。 第2章は、研究者から経営者へと進路を変更した“冒険の時代”について。工科大学から帰国して博士号を取得した後、久能さんは薬品の研究者として従事。基礎研究のパートナーだった上野隆司博士が大きな発見をしたことから、久能さんは研究者としてのキャリアにピリオドをうち、上野氏と共同設立者として起業。上野博士が発見された物質を使った新薬の商品化に取り組みました。ひとつの製品は日本で、もうひとつの製品は日本に投資家がいなかったことからアメリカで投資家を集め、こうして久能さんはふたつの新薬の商品化に成功しました。 第3章は、久能さんが非営利分野で、世界のために何ができるかを模索してかたちにした、若手起業家の育成の時代です。この時代に創出したのが「ハルシオン・インキュベータ」で、これは社会問題の解決を志す起業家を育てる仕組みのこと。特徴的なのは、起業家を志す若者たちが“ハルシオン・ハウス”での共同生活を通じて、互いに刺激しあい、また創造的な発想を引き出しやすい環境を整えたことです。なお、久能さんは、この取り組みを通じて、女性が会社を設立しても、投資を受けるのは難しく、多くは男性起業家に偏る傾向があることに気づきます。そこで久能さんは性差を問わず、数多くの能力ある起業家を輩出する活動と並行して、投資家を育てる活動も行い、社会において女性が活躍しやすい環境を整えられたのです。その結果として、「多大な経済的インパクトをもたらすことができたことを誇りに思う」と述べると、会場からは大きな拍手が沸き起こりました。 アジア女子大学ファンドレイジングイベントには、アジア女子大学の応援者として、また女性活躍に向けた活動をされているファーストレディの安倍昭恵さんも参加されていました。今回のイベントのご感想を伺うと、「年々規模は大きくなり、ファンドレイジングイベントを通じて支援者が増え、1人でも多くの学生さんが勉強できる環境が整って欲しいです。そして卒業後に、それぞれの地域で活躍されることに期待しています」と話してくださいました。 国際女性デーを機に、各界で活躍されている女性の姿を見ることができた3月。女性の皆さまには、これからも勇気を持ってご自身の目標やビジョンの達成に向け、邁進していただきたいですね! #ciaoDonna by FIATプレゼントキャンペーン実施中オリジナルトートバッグ&FIATキーホルダー200名様にプレゼントhttp://bit.ly/2K2h9JV […]
JKSK ふくしまオーガニックコットンバスツアー
#FIAT#Share with FIAT#イベントバスは満席で、新宿駅の集合場所を発車しました。行き先は福島県双葉郡広野町。2011年の東日本大震災で震度6弱の地震と津波の被害を受け、4年経ったいまも、町民の帰還率は半数に満たないという、戸籍人口5000人強の小さな町です。 福島県いわき市を拠点に活動するNPO法人ザ・ピープルの吉田恵美子理事長が説明してくれました。 「広野町の住民の多くは、いわき市など他の町へ避難しました。被災した町民の帰還率は半分程度ですが、いま町に住む人の数は震災前と同じぐらいまで増えています。なぜかというと、福島第一原発の作業に関わる人、周辺の除染に携わる人など各地から集まった多くの作業者の方々が広野町に滞在しているためです。しかし人数が震災前と同レベルになったといっても、住民が町で出会うのは知らない人ばかり。そんな状況に馴染めず、帰還をためらっている方も少なくないようです」。 往路の車内は始めのうちは会話が少なく静かでした。乗り合わせた40名程度の参加者は知らない人の集まりだからです。居住地も年齢もばらばら。首都圏からの参加が多いですが、長野県から来た方もいました。年齢も小学生からすでに仕事を引退された方までさまざま。家族や友人と一緒の人もいましたが、単独で来た方や初参加の方も大勢います。参加者は隣に座った人とぎこちない会話を交わしながら、少しずつお互いの距離を縮めていました。知らない人同士が馴染むまでには相応の時間が必要ですよね。避難者の方が、新しい町や地元で、知らない人の多い環境にすぐに馴染めないというのもわかる気がします。 今回のバスツアー「広野町応援プロジェクト ふくしまオーガニックコットン」は、認定NPO法人JKSK 女性の活力を社会の活力にが立ち上げた「JKSK 結結プロジェクト」の一環として行われるもの。2013年に始まり、今年で3年目となるこのバスツアーは、風評で野菜が売れづらくなった地元農家の方々の悩みに応えるために立ち上がったNPO法人ザ・ピープルと共同で、広野町の耕作放棄地でコットンの有機栽培を行うというもの。耕作放棄地とは、農家が野菜の栽培を断念して“空き畑”となった土地のこと。広野町やいわき市にたくさんあるそうです。 オーガニックコットンプロジェクトは、それらの土地を有効活用し、塩害に強いコットンを育てます。口に入れるものが売れない状況なら口に入れないものを製品化し、新しい農業や産業を創出しようという発想のもと、新しい事業を広野町やいわき市だけでなく、他の被災地にも広めていくことを目指しています。 できあがったコットンからは、手ぬぐいやTシャツ、タオル、ハンカチのほか、仮設住宅にお住まいのお母さんらが手づくりする「ふくしまオーガニックコットンベイブ」がつくられます。このコットンづくりプロジェクトは、その普及や自然エネルギーの促進を目指して市民自らが参加して新しい町づくりに挑戦する「いわきおてんとSUNプロジェクト」に集約。復興町づくりプロジェクトとして広まりを見せています。JKSK「結結プロジェクト」も、定期的にボランティアバスツアーを実施し、綿の定植や草取り、収穫の支援者を集っています。今回バスに乗り合わせた方々はこのJKSKボランティアバスツアーの参加者。長靴やタオル、着替えなどを持って、畑作業に向かいます。 「Share with FIAT」活動を展開しているFIATはこの活動に賛同し、JKSKボランティアバスツアーを支援しています。Share with FIATとは、“シェア”を合言葉に、自分だけでなくみんなの幸せを求める社会の実現を目指す企業プロジェクトのこと。現在7つのNPO団体と協力して、さまざまな社会活動を行っています。今回は、FCAジャパン株式会社マーケティング本部長ティツィアナ・アランプレセ氏が高校生の娘さんやその友達と共に、参加者の一員として畑作業を行いました。 午前10時30分頃、バスは畑に到着しました。地元農家やNPO法人の方が迎えてくれ、農家の方とボランティアバス参加者が一緒になって作業に取りかかります。畑はビニールマルチ(畑の乾燥などを防ぐカバー)が被せられていましたが、土は乾燥していて、まわりには雑草が生い茂っていました。まずは草むしりから始めます。約40名が一斉に取り組むと、畑はみるみるうちに本来のあるべき姿を取り戻していきました。 次は苗の定植。参加者はビニールマルチに穴を空ける人、できた穴を掘り起こし、水を注いで土を慣らす人、植え込みをする人、水やりをする人、川に水を汲みに行く人に分かれて、それぞれ仕事を進めていきます。新宿の集合場所で集まったときには会話が少なかった参加者もこの頃には打ち解けて、すばらしいチームワークを発揮していました。お昼は、農家の方がご用意いただいたお昼ご飯をいただきました。 昼食時に地元の方々や県の関係者の方とお話をする機会がありましたが、地元の方は首都圏から参加者が集まってくることは、大きな勇気になると話していました。力になりたいという気持ちに触れられることや、震災のことを忘れられていないという実感を持てることが、復興への前向きな気持ちを後押ししてくれるといいます。 化学肥料を使わないぶん、労力が必要なオーガニックコットン栽培。育てるには手間が掛かるため、1日でできるお手伝いは植物のライフサイクル全体からすれば小さなものかもしれません。しかしオーガニックコットンプロジェクトは、農業人口の不足という問題を抱えながらも、さまざまな人の手を借りて持ちこたえ、前進しています。板橋区から来た参加者はコットンの種を持ち帰って家で育て、次回参加する時にできあがったコットンを“里帰り”させると話していました。 2012年に始まったばかりのオーガニックコットンプロジェクトは、少しずつ栽培支援の輪が広がり、拡大しています。今年5月には「太平洋・島サミット」で参加国の夫人を対象とした交流事業として採用されるなど、行政による震災復興事業のひとつとして、人と人を繋ぐ役割を果たしました。いわき市では、住民と避難者という背景の異なる人たちが分離する状況が起きているそうですが、オーガニックコットンプロジェクトは両者の接点を作り出す機会ともなっているそうです。 さまざま人の想いや希望の詰まったオーガニックコットンプロジェクト。今回のバスツアー参加者の中にも、次回の収穫ツアーへの参加を希望する人がいました。首都圏の参加者にとっては“畑体験”という新鮮な世界に触れながら、福島の新事業創出を応援できることが魅力となっているようです。 […]