本年も、FIATと楽しいまいにちを!〜新年のご挨拶
#ShareWithFIAT#ご挨拶#ペット#犬#試乗新年のご挨拶 謹んで新春の慶びを申し上げます。 日頃は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 本年も皆々様のご多幸を、心よりお祈り申し上げます。 “ワン”ダフルなくらしをサポートします 2018年は戌(いぬ)年。 長らくご愛顧いただいた「FIAT CULTURE MAGAZINE」は「FIAT MAGAZINE CIAO!」として装いも新たにスタート。 今も昔も乗ると楽しくなるFIAT。ONもOFFもオシャレも趣味もさり気なく楽しむ、肩肘を張らない自然体。そんな自由で気ままなクリエイティブライフを楽しむみなさんに、ちょっとしたワンダフルなモノやコト、そしてFIATがもっと好きになる歴史や伝統もお届けします。 さて、そんなFIATの最新の魅力を感じていただくために、1/6(土)〜21(日)まで、FIAT/ABARTHの全モデルを対象にしたキャンペーン「ワンダフル テストドライブキャンペーン」を開催します。 ご試乗頂いた方には記念品、さらに抽選で2018年の干支である「戌(いぬ)」をモチーフにした“ワン”ダフルなグッズが当たるキャンペーンも実施しますので、是非お近くのFIAT/ABARTHのオフィシャルディーラーまで足を運んでください。 >詳しくはコチラ 2018年はワンちゃん推し 昨年2017年にアルゼンチンのFIATがおこなったオンラインイベントをちょっとご紹介したいと思います。御存知の通り、アルゼンチンには干支という概念は存在しないので、戌年の今年との関わりは全くの偶然なのですが、FIATというブランドがもつ感覚をご理解いただくにはもってこいだと思うのでご紹介します。 「FIAT DOGS」 ワンちゃんたちとそれぞれの名前、プロフィールが並んだ、まるでFIAT社のクルマの車種紹介ページのようなウェブサイト。これは、里親になってもいいという人たちが、あたかもクルマの細かなディティールを確認するかのように、ワンちゃんたちのことを知ることができるというもの。 「犬は人類にとって最も親しい仲間」という考え方は世界共通。日本はもちろん、FIATの母国イタリアでもペットとの生活は、日本以上に親密といっても差し支えないかもしれません。 しかし、昨今日本でもメディアを賑わせる、里親を持たないペットたちの殺処分問題は、このアルゼンチンのみならず海外でも大きな問題として関心を呼んでいます。 そんな悲劇を少しでも減らすためにと立ち上がったのが、ペットにひときわ強い思い入れのあるイタリアのFIAT。単に経済的な協賛をするのとは違い、このようにちょっと「シャレの効いた」スタイリッシュかつ効果的なアピール方法をとったところが「らしさ」ではないでしょうか。 サイト公開後最初の数時間で5万を超える人々がFIATのウェブサイトに訪れ、同サイトの動画再生も最終的には100万を超えるという大きな反響を呼ぶことができました。 こうした姿勢やクリエイティビティこそがFIATというブランドがもつDNA。 ペットだけではなく、食、デザイン、ファッション、ホビーやスポーツなど、くらしや人生のクリエイティブを彩る要素はたくさんあります。 「FIAT MAGAZINE CIAO!」では、そんな人生をもっと楽しくするためのコトやモノの情報。そして社会や文化に対する貢献活動についてお届けします。 CIAO!
FIAT×ルーム・トゥ・リード・ジャパン 海の向こうに届けるプレゼント
#ShareWithFIAT#イベント#レポート個の可能性を地域に、そして世界へ。社会で活躍する人材の基本である「読み書き」の学習環境を世界の行き届いていない地域にも広めたい。その日、赤坂アークヒルズ・カフェに集まった大勢の人たちは、そんな共通の想いで繋がっていました。特定非営利活動法人ルーム・トゥ・リード・ジャパンによる催しの模様を報告します。 ルーム・トゥ・リードは、教育を受けられない環境で育っている子どもたちに、学習の機会を与える活動を行なっている国際NGO。“子どもの教育が世界を変える”という信念のもと、主に開発途上国での識字(読み書き)能力と教育面での男女の格差(地域により女性は教育を受けられないなどの問題)をなくすことに注力し、地域の政府機関やコミュニティと連携し、子どもたちに学習の機会を与えてきました。その活動資金は主に寄付によるもの。この日、赤坂アークヒルズ・カフェに集まった人々は、ルーム・トゥ・リードの活動に賛同する一般支援者の方々です。 こうした活動が必要な背景には、厳しい現実があります。日本にいると実感は薄いものの、世界では今なお7人に1人は文盲で、その2/3は女性だといいます。そうした環境を変えるには、先進国で支援の輪を広げる必要があるのです。 フィアットも、ルーム・トゥ・リード・ジャパンの活動に賛同し、支援を行なっています。フィアットが望むすべての人が自分らしく、輝いた生活をおくる社会を実現するためには、女性の、そして次世代を担う子供の教育が欠かせません。読み書きのできない子供たちに本を読むことの素晴らしさを知ってもらい、男女に均等な教育インフラを作り出す活動は、フィアットの掲げるビジョンにも通じるのです。 レセプションで乾杯の音頭をとったのは、FCAジャパン マーケティング本部長ティツィアナ・アランプレセです。 「明日の社会を変えるのは子供たちです。女の子も教育を受けられるようにするため、少しずつの支援を集めて、大きな力にしましょう。フィアットでは、そうした活動を“Share with FIAT”として展開しています。皆さんで一緒に世界を正しましょう」。 ルーム・トゥ・リード共同創設者兼CEOエリン・ガンジュさんのスピーチが続きます。 「ルーム・トゥ・リードでは、世界のあらゆる地域の子供たちが読み書きをできる社会の実現を目指し、これまでにアジアやアフリカを中心に、2万の学校やコミュニティと手を組み、1200万人に教育のギフトを届けてきました。このような成果を出せたのは、みなさまからの支援を得て、その国の政府や公立の学校とともに活動し、地域の環境を変えてきたからです。力を合わせ、アクションを起こせば世界は変わるのです」と述べ、新たなアフリカとアジア向けの教育支援プロジェクト「Action for Education(アクション・フォー・エデュケーション)」を打ち出しました。 ルーム・トゥ・リードでは、支援者に対して活動報告を徹底しています。寄付金の使途を明確にし、成果を見える化することで、支援者の寄付金がどのように役立ったのかをわかりやすいかたちで伝えています。また、例えば今回のような支援者の集いでは、支援者同士が活発な情報交換を促し、活動そのものやネットワークの輪の中にいることを楽しめるように努めています。 支援者の方に話をうかがってみました。中野太智さんと浅井美香さんは、ともにルーム・トゥ・リードの支援者。活動を始めた動機をうかがいました。 中野太智さんは「ルーム・トゥ・リードが行なっている教育支援というのは、社会を良くするもので、それはいずれ循環して自分にも返ってくるものだと思います。遠く離れた日本にいると直接的な活動に参加するのは難しいですが、支援という間接的な方法ならできます。またその活動の成果を知ることもできるので、自分が役に立てたという実感を持てるのがいいと思います」 浅井美香さんは、支援活動に参加するきかっけになったのは中野さんから借りたジョン ・ウッド氏(ルーム・トゥ・リード創設者のひとり)の執筆した本から。そこに書かれていたことに感銘を受け、自ら活動しようというモチベーションに繋がったと話してくれました。 長谷川愉以さんは、自分になにができるかを考えた結果、毎月一定の金額の寄付を行なっています。始めてから自分のなかにある変化が生まれた」と話してくれました。 「支援した子どもたちがどう変わったのか。関心が生まれ、ウェブサイトを調べ、自ら情報を収集しにいく。それまでしなかった行動をしていることに自分のなかに起きた変化を実感しました。また、ルーム・トゥ・リードのイベントへの参加を通じても自分が変わったことを感じています。あるイベントでは参加者は席が決められていて、必然的に隣の方とお話をすることになります。同じ活動をしている人たちの輪なので会話が進展しやすいというのもありますし、そこから新たな情報を得て、自分の行動が変わることも経験しました。支援を始めたことで、思いがけないところでポジティブな方向に自分が変わっている。そんな実感を持つようになりました」。 支援者の方々は自分の行動による子供たちの変化を知ることに喜びを感じ、また支援という行動を通じて得られる自分へのフィードバックも楽しんでいるようです。 会場ではピアノの演奏が始まりました。奏者は“旅するピアニスト”こと永田ジョージさん。イタリアの楽器クラビエッタを片手に、中東やギリシャなどを旅した永田さんは、各国で音楽を通じて人と人が繋がることを経験してきました。ルーム・トゥ・リードとの繋がりは5年ほど前から続いています。 ピアノの音色が会場を心地よい空気で包み込んだところでいよいよお開きに。今回も参加者同士の新たな出会いがあり、親睦を深める機会となったようです。 ルーム・トゥ・リードの活動に興味のある方はぜひHPをチェックしてみてください。 ルーム・トゥ・リード・ジャパン公式サイト
FIAT〜写真展のおしらせ 「La 500 : piccola grandiosa」
#イタリア#イベント#写真2017年12月17日(日)から12月29日(金)まで、東京銀座のギャラリー「BASEMENT GINZA」で写真展が開かれます。 その名も「La 500 : piccola grandiosa」 「小さくて、偉大なチンクエチェント」という意味なのですが、イタリア人の生活の一部としてのFIAT 500を垣間見ることができます。 クルマを撮るのではない 美しい街並み、美しい夜。そこで暮らす人間味溢れる温かい人たち。 圧倒的な歴史と文化を誇り、時に優雅で、時に間抜けで、それでいてどこか憎めないキャラクターをもちあわせる国イタリア。 たとえそれが素朴で質素であっても、こと人生を楽しむという点において「達人」といわれる彼の国の人々ですが、それが色濃く溢れているのがイタリアの南部だといいます。 そんな人々の暮らしや生き様に惹かれ、20年近くもイタリアに通いシャッターを切リ続ける写真家が加納 満(かのうみつる)さん。彼は、イタリア人の暮らしや人生を撮り続けるうちに、その傍らにいつも寄り添う愛らしいクルマ、FIAT 500の存在を意識するようになったといいます。 「そもそも僕は、「画」つまり「クルマが主体の写真」としてチンクエチェントを撮るつもりでシャッターを切りはじめたワケじゃないんです…。サルデーニャで、シチリアで、バーリで、人々やその暮らしに「出会う」のと同じように、気づくとごく自然にFIAT 500との出会いを漏らさず記録し続けていたんです。」 「情熱の赤に憧れて」 この写真展の共謀者、小野光陽(おの こうよう)さん。編集者にしてプロデューサーの彼もまた、イタリアとの縁が深い。なんといっても若い頃イタリアの情熱の代名詞ともいえる跳ね馬のエンブレムに憧れ、単身モデナに乗り込んだというツワモノ。 「ネジ一本組み付けるだけの仕事でもいいんです。それでもあのクルマたちを生み出す現場に加わりたかったんです…。」 情熱の国に相応しい熱いものをお持ちの小野さん。その後も4年以上にわたりイタリアで生活をされたという小野さん。現地の生活をよくご存知なのは言うまでもありません。 そんな彼と加納さんとの出会いは、とある雑誌の企画での偶然から。 その後も共にお仕事をなさっていたそうですが、ふとしたきっかけで加納さんのSNSに頻繁に登場するFIAT 500を見た小野さんが、この企画を思いついたといいます。 「もちろん加納さんの写真が好きだったということもあるんですが、彼の写真には、ステレオタイプで表面的なイタリアの街や暮らしではなく、僕の知っている一歩踏み込んだイタリアがそこにはあるんです…。人と街と暮らしとクルマ、そうした距離感に“これだ!”と思ったんです。」 モノは長く愛することで、愛着はもちろん心すら宿るといいますが、1957年にデビューし、その後20年に渡り製造され続けたNuova 500(ヌオヴァ・チンクエチェント)は、まさにその次元に突入しているものが多いようです。 「色あせようが、ボディやバンパーが凹んでいようが、人間が老い、顔に皺が寄るように年輪を重ねている様が、何かクルマ以上のものを僕に訴えかけてくるんです。生活や風景に馴染んで日々共に暮らしているというか。僕はそうした部分すべてを見ていただければと思っています。」 そう語る加納さん。 やっと人が通れるくらいの路地に、ありえないほど壁にギリギリに停められた濃紺チンクエチェント。加納さんとFIAT 500の「はじめの一枚」とともに、世界に愛されるイタリアの名車、今も同じくイタリア人の生活に溶け込んでいる「チンクエチェント」の真実の姿を覗いてはみませんか? 加納 満
「若手料理人 世界一」を目指す日本地区代表が決定! 〜『サンペレグリノ ヤングシェフ 2018』日本地区大会
#イタリアン#グルメ#プレゼント文=山根かおり 写真=SHIge KIDOUE 30歳以下、ノンジャンルで行われるユニークな料理コンクール 自分の持てるパッションを全力で傾け、夢を追いかける若者たち。『サンペレグリノ ヤングシェフ』は、そんな情熱あふれるヤングシェフが集うコンペティションです。数あるコンクールのなかでも30歳以下の若き料理人の可能性に焦点を当てているのが特徴。そして、フランス料理でも和食でもジャンルを問わずに挑戦できるのも面白いところです。 実際サンペレグリノはどんな料理にも合わせやすいファインダイニングウォーターとして愛されていますし、レストランや料理人とのつながりも深いので、サンペレグリノらしい料理コンペティションといえるでしょう。 コンペティションでは、まず自らの実力を凝縮させたシグネチャーディッシュを書類で応募し、それをパルマにある国際的な料理学校「ALMA」が審査。ここで21の国・地区それぞれの代表10名ずつが厳選され、ミラノの決勝に進める代表1名をその地区内で選出します。 名だたる顔ぶれの審査員が出場者10人の料理を丁寧に審査 日本地区大会は、10月12日に開催されました。出場者10名は、すでに自分の店を持っていたり、有名店でスーシェフを務めていたりする実力派ぞろいですが、やはりコンペティションということで緊張感が漂います。 開会式では、審査員から「参加者のみなさんと食に対するパッションを共有できて嬉しい。1人を選ぶのは難しいですが、私たちもベストを尽くします」(アンゲラー氏)。「この緊張感を、世界に羽ばたき次のステージへと向かうステップにして」(高澤氏)。「自分ができることを精一杯出し切れば、それは必ず何かにつながります。頑張って!」(長谷川氏)と、激励のメッセージが寄せられました。 調理時間は自己申告制で、中には5時間にわたって仕込む出場者も。調理中も審査員シェフは各テーブルをまわり、時に話しかけたり質問を向けたり。取材のカメラも入りますが、集中力は途切れません。 駐日イタリア大使館に場所を移し、いよいよ日本代表の発表! 熱戦を制した1名の発表は、駐日イタリア大使館に場所を移して行われました。 発表後には華やかなアフターパーティが控えていることもあって会場はにぎやかな雰囲気に包まれましたが、朝から調理とプレゼンテーションを終え、力を出し尽くした出場者10名は緊張の面持ちで発表を待ちます。 審査員を代表し、ルカ・ファンティン氏が発表。 読み上げられたその名前はYasuhiro Fujio、大阪「ラシーム」でスーシェフを務める藤尾康浩さんでした! メンターシェフとして藤尾さんとともに「世界一」を目指すルカ・ファンティン氏は「地区大会優勝は私たちの第一ステップ。ミラノでは他20地区の代表者と競うことになりますが、ライバルはたった20人です。プレッシャーを感じなくても大丈夫。これから一緒に頑張っていきましょう」と新たな愛弟子を祝福しました。 料理のタイトルは「Across the Sea」。日本特有の食材である鮎を用い、鮎になじみのない海外の人でも受け入れやすい創造性豊かな一皿です。 審査員の高澤氏が「10人のすばらしいクリエーションの中でも、藤尾さんのプレゼン能力はとくに優れていました。コンペティションなのにレストランで出すのと同じクオリティのシズル感、温度感を表現できていた点も評価が高い」と太鼓判のコメント。料理のコンセプトから素材選び、調理法、プレゼンテーションまで、緊張感とプレッシャーの中で高いクオリティを出し切れたことが評価につながりました。 出場者のシグネチャーディッシュ、そのすべてを一挙公開! 発表の際、ファンティン氏から「過去のイベントの中でもレベルが高かった」と総評があった本大会。「オリジナリティとクリエイティビティに富み、旬の食材をふんだんに使って、フレーバーのバランスも抜群でした」(アンゲラー氏)、「ひとりずつに個性があってしっかり前を向いていて、非常にすばらしかった!」(長谷川氏)という声もありました。 さて、代表に選ばれた一皿だけでなく、未来の「食」を担う若手料理人へのエールを込めて、出場者すべての力作をご紹介しましょう(敬称略)。
夢をかなえる魔法の小箱〜ライカを愛する女性カメラマン
#Leica#カメラ#写真#茅ヶ崎カメラ女子、そんな言葉を聞くようになって久しい。 デジタルカメラが普及して技術的なハードルが低くなったからだという人もいれば、インスタを例に挙げるまでもなく、写真を気軽に撮れる、もっとうまく、美しく撮りたいという気持ちは、むしろ男性よりも女性の方が高いせいなのかもしれない。いずれにせよ、カメラというメカを楽しむのではなく、写真を撮る行為自体を楽しむ女性が増えたのは事実だ。 大門美奈(だいもん みな)が、そんなカメラ女子のひとりかと言えばちょっと違うように思える。 カメラメーカーが主催する公募展の入賞をきっかけに注目を浴びるようになり写真家としての道を歩みはじめた彼女。アンダー目でしっとりとしたトーンが持ち味で、見る者の心を落ち着かせるような写真だ。もともと絵が好きで十代のころには画家に師事していたこともあった。写真との出会いは造園を学んでいた大学時代、卒論に添付する写真を撮るため一眼レフを買ったのが最初。 「ちょっと動機が不純なのですがスペインのアルハンブラ宮殿に行きたくて卒論のテーマに選びました」 照れくさそうに笑う大門。 「卒論にはポジ(スライド)を添付しなければならなかったので、なんの知識もなく一眼レフを買いました。カメラを向けシャッターを押すだけで思った通りの絵が撮れる、その不思議な感覚に写真が好きになりました」 さらりと言うが、これは大変なことだ。写真を趣味にする人の悩みの大部分は思ったように撮れないこと。よほど大門と写真の相性はいいらしい。そんな大門が写真を本格的に学びはじめたのは手痛い失敗からだった。友人の結婚式を撮り、その写真が評判を呼びその兄弟からも撮影を頼まれた。ところがカメラの設定がなにかの拍子で動いたのか、なんと何も写っていなかった。もちろん今のようなデジタルカメラではない時代なので、取り返しの付かないことになってしまったのだ。 「落ち込みました。期待に応えられなかったのが悔しかった。でも、不思議と写真をやめる気にはならなかったんです」 負けず嫌いの性格から写真専門誌のスクールに通うようになったという。 つまり趣味の延長線上という、ありがちなスタートポイントとは違い、純粋に写真の技術を磨こうという努力を行ったという点で、彼女はれっきとした正統派の写真家だといえる。 ライカとの出会い 本格的に写真を学ぶようになって大門がたどり着いた道具はライカだった。 「もちろん紆余曲折はありましたよ(笑) いろんなカメラを使ってみて、一番自分に合っていると感じたのがライカなんです」 ライカといえば世界の名機、性能も素晴らしいし出てくる絵も素晴らしい。 「もちろん、それもあるんですが一番の理由は小さくて手に馴染むからなんです」 と意外な答えが返ってきた。 「いつでも持ち歩ける相棒として、これ以上のものはないと思ったんです」 かくしてライカは大門のイメージを具現化する魔法の小箱になった。 どちらかと言えば重厚でもの静かな雰囲気を漂わせる大門の作風だが、箱庭シリーズは趣を異にする。 とある生活雑貨の店舗をジャックするかたちで行われた写真展は圧巻だった。そこには日々の暮らしを超えた、見る者を魅了する「何か」が写り込んでいた。 「最初は勤め先へ持っていくお弁当の記録だったんです。ですからスマートフォンで撮っていたんですが、そのうち満足できなくなって…。 写真が持つ一番の特性に「記録」という役割が挙げられるが、それを超えたところに表現がある。つまり被写体である弁当箱たちもまた、大門の世界を表す魔法の小箱というわけだ。だから、盛りつけにも絵心が溢れている。標本のように真上から撮られた弁当箱の中に、つい引き込まれてしまう。 ライカとFIAT 500 そんな大門だが、最近、海にほど近い神奈川県の茅ヶ崎に居を移した。 海辺の散歩が日課になり、猫との暮らしも気に入ったからだというが、この海辺の地でのライカとの散歩が、彼女の作品の幅を拡げたことは言うまでもない。しかし、一方で思いがけない問題も発生した。 「必要を感じなかったこともあるんですが、実はいままで車の免許を取らなかったんです。でも、ここへ越してきてからというもの、移動の手段として車がどうしても必要。だから運転免許取得を真剣に考えるようになったんです…。 そんな大門をFIAT 500の助手席に乗せて海辺の道を走ってみた。 「クルマは好きなんです。流れる風景を眺めるのも好き。どこかへ運んでくれるメカっていうのもいいですね。それに、これ小さくてかわいい。なんだかライカみたい。 大門の愛機であるライカM10は、1954年に誕生したレンジファインダーの名機ライカM3の末裔。ほぼ同時期の1957年に生まれたNuova 500と現行の500との関係にも共通点がみられる。 ライカM3とはアナログのカメラの金字塔的な存在であり、その子孫たるライカM10は、その佇まいはもちろんのこと、使い勝手やコンパクトネスなどをライカM3から引き継ぎ、そこにデジタルの便利さを兼ね備える名機として、今も大きな人気を誇る。 まさに新旧500とよく似た境遇の存在でもある。 「実は鎌倉あたりでよく見かけるので、いいなぁって思っていたんです。道の狭い小ぢんまりとした街にも似合っていてお洒落だし…。
ギターと歌と絵本の読み聞かせのステージ
#ShareWithFIAT#イベント#レポート今回は東京都渋谷区の日赤医療センターで行われた活動をご紹介します。 オトイロクレヨンの二人は、久末冴子(歌う絵描き屋さん)と平原謙吾(シンガーソングライター)のユニット。 冴子さんがオリジナルの紙芝居を演じ、謙吾さんのギターが伴奏します。 二人が明るく歌い、踊り、演奏する様子に子どもたちも自然と笑顔になります。 親御さんの中には、パフォーマンスを目の前で熱心に見つめる方もおられて、入院生活の気分転換のひと時になっていたようです。 SHJは、アート・パフォーマンスを通して、病気と闘う子どもたちとご家族をサポートしています。
ハレバレーでの日曜大工講座(木工教室)
#ShareWithFIAT#イベント#レポートピースウィンズ・ジャパンでは、南三陸町で現地NPO法人びば!!南三陸と協力し、地域の皆さんが楽しめる講座を日替わりで実施しております。 9月は、その中のひとつで月に1回開催される日曜大工講座(木工教室)の様子をお届け致します! 当団体の講座は、地域の人同士で講座ができるよう、得意技や得意な趣味を持つ方に先生になっていただき、参加されるみなさんからは、300円~500円の間で参加費を頂くシステムで展開されております。 対象者は、誰でもOKです。木工教室は、参加者が思い思いに作りたいものを先生と相談をしながら作ります。 9月は、何でも代用できる棚を制作しました。みなさん、実用できるものを作って帰るので、次に参加するのが楽しみだそうです! びば!!南三陸の活動は、地域の人が持続的に活動を続けられるような仕組みになっております。ですので、誰が先生で、誰が生徒かいまいち分かりづらいのが、写真からお分かりになりますでしょうか? (先生は、首に黄色のタオルをまいております!)
1,000人が集合! 「CIAO FIAT! 10th BIRTHDAY 2017」
#FIATBIRTHDAY#イベント#オーナー紹介#レポート文=増川千春 写真=太田隆生 1,000人を超えるFIATオーナー&ファンが集合 FIAT 500のバースデーイベントが、7月9日、千葉県のキャンプ場「一番星ヴィレッジ」で開催されました。現在のモデルが日本で走り始めたのが、2007年7月4日。それから記念すべき10周年となる今年は「CIAO FIAT! 10th BIRTHDAY 2017」と銘打って、例年以上に盛大なお祝いとなりました。 今回参加したFIATのオーナーやファンの方々は1,000人以上。天候にも恵まれたこの日、雲ひとつない青空のもと、色とりどりの500をはじめとするFIAT車が続々と詰め掛け、会場は徐々にヒートアップ! スペシャルMCを務めたハイキングウォーキングのおふたりによる開会宣言とともに、にぎやかな一日がスタートしました。 ユニークなアイデア満載! 思い思いに愛車をデコレート とりわけ目を引いたのが、愛車をフィーチャーした「MY FIATコンテスト」。オーナー自らがフルにセンスを発揮して、500の車体をデコレーションし、来場者の審査によって、ベスト3が選ばれるという内容。ずらりと並んだ力作の周りには、常に人だかりと歓声がいっぱい! オーナーさん同士の“FIAT愛”にあふれた会話にも花が咲き、活気ある盛り上がりを見せていました。 500を愛し、人生を楽しむ、個性豊かなオーナーたち 道を走るという目的を超えた車とのつながりが、さらに新しい好奇心を運んでくる——500のオーナーさんに共通するのは、そんなライフスタイルのストーリーです。群馬県から参加した高橋優華さんは、イタリア生まれならではのフォトジェニックなデザインに惹かれて人生初の車に決めたそう。そしてこれから海に出かけて、愛車の写真を撮りたいと目を輝かせていました。 また、コンパクトなサイズ感や色も魅力。東京都の上條さんご夫妻は、愛犬によく似ているとひと目で気に入った限定カラーを購入。後部座席に乗せた愛犬との距離感が近いので、ドライブ中もコミュニケーションがとりやすく安心感があると教えてくれました。 そのほか、メンテナンスしながら大切に乗るヴィンテージ派、独自の色やデザインを施すカスタム派など、マニアックな楽しみを追求する上級者もたくさん。まるで人生のパートナーのように車を愛する姿が、とても印象的でした。 多彩な催しが目白押し。一日はあっという間に過ぎて 中央に構えたメインステージをはじめ6つのブースでは、500の10回目のバースデーにふさわしい多彩な催しが用意されました。スペシャルライブにまず登場したのは「よかろうもん」のみなさん。アカペラコンテストのハモネプにも出場したことのある、5人組のアカペラグループです。メンバーは全員同じ高校出身ということで、息の合った素晴らしいハーモニーを会場のみなさんに届けてくれました。 次に登場したのは世界的バイオリニストであり、初代500トポリーノのオーナーでもある古澤巌さん。暖かな初夏の風に乗った古澤さんの生演奏は、時間を忘れさせるような優雅なひとときとなりました。 メインステージのほかにも会場内には、イタリアにちなんだカフェやフードカーが並び、バンジージャンプやワークショップなどといったアトラクションもあちこちに。ランチタイムには料理研究家・本田よう一さんによるイタリア風カレーが来場者のみなさんに提供されました。 そしてまた、会場に集まったみなさんで取り組むアクティビティも大盛況。その中のひとつ「ダンシング玉入れ」は、かごに見立てた500 を目がけて、一斉にボールを投げるゲーム。約200名が2チームに分かれて、エキサイティングに勝敗を競いました。 さらにクライマックスにはパパイヤ鈴木さんが登場。この日のために創作いただいたオリジナルの「FIATダンス」が披露されました。500のバースデーをみんなで祝おうとメインステージに集まった方々に振付をレクチャー。わずかな練習時間でしたが、会場が一体となってダンスを踊りきり、笑顔と拍手に包まれました。 10周年のラストはよかろうもんの音頭で、参加者全員が「ハッピーバースデー」をイタリア語で合唱。同じFIAT車に乗る仲間でつくり上げた特別な一日はあっという間に過ぎ、オーナーやファンの方々は名残惜しそうに会場をあとに。また来年、同じ価値観を共有する仲間と自然の中で楽しく祝う夏の日を満喫できたら、こんな素晴らしいことはないですね。Ciao! ==== 古澤巌さん、パパイヤ鈴木さんなど
2017年もARKがFIATバースデーイベントに参加!
#FIATBIRTHDAY#ShareWithFIAT#イベント#レポート去年に引き続き、今年もバースデーイベントに参加させていただきました。 晴天に恵まれ猛暑日のような一日でしたが、参加されていたお客様も熱気に溢れていました。 今年は、バルーンアーティストであるアークの里親さんがバルーンをご提供してくださり、またお子さんやグッズをご購入くださった方には小さなバルーンもプレゼントしたりと、皆さんに喜んでいただける演出ができたと思います。 イベントの途中も司会の方がTwitterの中継で紹介していただくことができて、またイベントの最後には壇上でPRをする機会もいただきました。アークのことを知らない方はまだ多くいますが、何度かイベントに参加する中で、FIATファンの方々にもさらに認知度が上がったと思います。
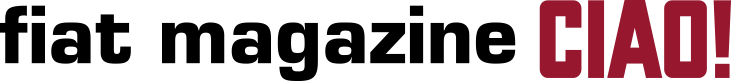




-1024x629.jpg)









