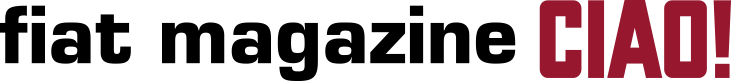コーヒーブレークをちょっと楽しく〜ヒスイ色のマグカップ「Fire-King」
#Fire-King#アメリカ#インテリア#コーヒー#マグカップ#限定車オシャレな若者たちや外国人が数多く訪れる東京原宿。中でも人気のキャットストリートを歩いていると、ふと見上げたショーウインドーにあったマグカップが目に入った。 ちょっとレトロなデザインと、青磁っぽくもあるグリーンのマグカップはFire-Kingという。1941年にアメリカで生まれた耐熱ガラス食器のブランドだと店主に教えられた。 世はサードウェーブと言われる空前のコーヒーブーム。こだわりの自家焙煎の喫茶店や注文焙煎の豆店、書店には多くのコーヒー特集号が賑わい、バリスタなんていう言葉も珍しくなくなった。その流れによる影響もあるのだろう。器であるカップ類にも注目が集まりつつある。 さて、ちょうど友人の誕生日プレゼントを物色していた私が、このマグカップに目がとまったのは、他でもない彼の愛車のFIAT500のボディカラーにそっくりだったのだ。 このHAPPY! という2009年の限定車には、現行FIAT500がオマージュしたNuova500がデビューした1957年の純正色、Verde Chiaro(ヴェルデ・キアーロ〜「明るい緑」の意味)をオマージュした「ビンテージグリーン」がラインナップされていて、それがまさにFire-Kingの色に非常に似ている。 翡翠(ヒスイ)を意味するジェダイ(Jede-ite *ジェードともいう)と呼ばれるグリーンは、このブランドのイメージカラーにもなっている。そもそもヒスイという宝石は、美しさ、強さにおいて一目を置かれ金よりも珍重された歴史もあり、中国や日本はもちろん、欧州各国や中南米などまさに古今東西で愛されている色。初期のNuova 500をレストアしてる人でもこのグリーンにする人は多い。 このジェダイの他にも、Fire-Kingには様々な企業ノベルティものも数多く存在しており、世界中にもたくさんのファンがいる。ネットオークションなどでも数多くみかけることができるが、なにより、日本で最もオシャレなエリアにこうしたビンテージFire-Kingのお店が存在していることからも、その愛されっぷりは想像に難くないだろう。 ちなみにFire-Kingは一度1986年にその歴史の幕を閉じているのだが、2011年になんと日本で復活を果たしている。しかも、オリジナルが大量生産品だったのに対し、当時の雰囲気残しつつ、今度は日本の職人の丁寧な手仕事で蘇らせている。 香りも味ももちろん大切だが、ちょっと一息つくときに、ヒスイ色のカップからコーヒーが透けて見える姿もなかなか味わい深い。 さっと飲み干すエスプレッソもいいけど、読書でもしながらゆったりのんびり楽しむコーヒータイムも捨てがたい。そんな本当にちょっとしたことだけど、「楽しむ」心が溢れるテーブルの彩り。Fire-Kingはそんな小さなアイテムであることは間違いない。
美ファッションとパッションが交錯したイタリアンな夜 PASSIONE Presents ITALIAN NIGHT
#FIATCAFE#PASSIONE#イタリア#グルメ#ライフスタイル#九島辰也街ではクリスマスの飾り付けが始まった季節の夕暮れ。日本でも有数の高級住宅地、渋谷区松濤に位置するフィアットカフェ松濤に、たくさんの人々が集まりました。老若男女、年齢も性別もばらばらでしたが、彼らにはひとつの共通点で繋がっていました。それは、イタリアを愛しているということ。アリタリア-イタリア航空日本語版機内誌『PASSIONE(パッシオーネ)』の創刊3周年を祝うパーティの模様をお伝えします。 美しいもので人生の楽しみを広げるのがイタリア流 ここで、イタリアを愛する人々を迎えたフィアットカフェ松濤についても簡単に補足しておきましょう。フィアットカフェ松濤は、フィアット松濤店に併設されたユニークなカフェ。イタリアの食材を用いたフードイベントを開催するなど、クルマ以外のイタリアの魅力や文化、ライフスタイルを発信する基地として愛されている場でもあるのです。都心の一等地にあることとあわせて、パーティを開くのにうってつけというわけです。 イタリアで最も有名な高級スパークリングワインのひとつ、フランチャコルタの繊細な泡が来場者を歓迎し、ナポリの名店で修行を積んだ青木嘉則さんが焼くピザの香りが空腹を刺激します。そう、美味しいものや美しいもので人生を楽しむのがイタリア流。極めつけが料理研究家のベリッシモ・フランチェスコ氏の料理。登壇したフランチェスコ氏は、「ただ食べるだけでなく、土地の歴史や人柄とか、イタリアの美や食への文化を知ってもらいたく料理教室を開いています」と述べました。 フランチェスコ氏の言葉を聞きながら、ふと「料理」の部分を「クルマ」に置き換えても成立するのではと感じました。すなわち「イタリア車を知ることで、イタリアの文化を理解できる部分もあるのではないか」と思います。 さて、アリタリア-イタリア航空の客室乗務員のコスチュームを用いたファッションショーで会場のボルテージはさらに高まります。同航空会社の制服はこれまでにジョルジオ・アルマーニやアルベルト・ファビアーニといった錚々たる顔ぶれのデザイナーズブランドが手掛けており、2016年に18年ぶりに刷新された現在のワイン色の制服も、ミラノを拠点とするデザイナー、エットーレ・ビロッタの手によるもの。ファッションショーでは歴代の制服が一堂に会し、華やかなオートクチュール・コレクションを披露。イタリアを象徴する赤と緑を用いた色合いが見事でした。 さて、イタリアの美意識を堪能した後で、この日、最も会場を沸かせたトークセッションが行われました。壇上にあがったのは、『PASSIONE』の九島辰也編集長と、FCAジャパン マーケティング本部長のティツィアナ・アランプレセです。 九島さんは、「僕は自動車評論家の仕事もしているので、ティツィアナさんとは旧知の間柄。リラックスしすぎて、余計なことまでしゃべらないように気をつけます(笑)」と挨拶。 ティツィアナが、「私は学生時代に九州大学に留学して、日本をとても好きになりました。そして13年前に再び来日して、現在は、FCAというフィアットやアルファロメオなどのクルマを扱う企業でマーケティングの仕事をしています」と自己紹介したところで、愉快なトークセッションがスタートしました。 ここでは、ふたりのトークを抜粋してお伝えします。 九島 「フィアット500は日本でも人気がありますが、イタリア人ってホントにこのクルマが好きじゃないですか。実際、ミラノの街とかで見かけると映えるんです。なぜでしょうね?」 ティツィアナ 「人生って毎日が違う生活の連続ですよね。フィアット500は、ライフスタイルの変化に合わせやすいんだと思いますよ。どんな人でも、その人らしい使い方ができるというか」 九島 「カラーバリエーションも豊富で、性別や年齢を問わず、だれもが自分の好きな色を選べますね」 ティツィアナ 「そうです。特に若い人はカスタマイズしたりオプションを選んだり、自分にぴったりの1台を楽しんでいます。九島さんはファッションにもお詳しいけれど、ファッションを楽しむのにも似ていますよね」 九島 「おっしゃる通りで、フィアット500を楽しむ人は、ジャケットや靴を選ぶのと同じように、自分らしさを表現しているのだと思います」 ティツィアナ 「私は日本人になりたいと思ったくらいで、日本の文化をとても深く愛しています。一方で、イタリアの文化にはちょっと違うところがあって、でもそれも好きなんです」 九島 「たとえば、どんなところがイタリアの文化は違いますか?」 ティツィアナ 「自分らしさを大事にしたり、それを恥ずかしがらずに表現したり。だから私は、マーケティングの仕事を通じて、日本のみなさんにそうしたパッションを伝えられたらいいと思っています」 九島 「パッション、素敵な言葉ですよ。クルマにしろ旅行にしろファッションにしろ、情熱がなければ人生は楽しめませんから」 ティツィアナ 「ね? だからパッションを大事にして、恥ずかしがらずに自分を表現するために、九島さん、一緒に歌いましょうよ」 九島 「え? ここで歌うんですか?」 ティツィアナ「さあ、『オー・ソレ・ミオ』を始めるわよ!」 こうして、会場も巻き込んだ『オー・ソレ・ミオ』の大合唱でパーティは賑やかに幕を閉じることに。パッションと自分らしさを大事にして人生を楽しむ。参加者たちは、“イタリアンナイト”が発信したメッセージを満喫したはずです。
FIAT〜写真展のおしらせ 「La 500 : piccola grandiosa」
#イタリア#イベント#写真2017年12月17日(日)から12月29日(金)まで、東京銀座のギャラリー「BASEMENT GINZA」で写真展が開かれます。 その名も「La 500 : piccola grandiosa」 「小さくて、偉大なチンクエチェント」という意味なのですが、イタリア人の生活の一部としてのFIAT 500を垣間見ることができます。 クルマを撮るのではない 美しい街並み、美しい夜。そこで暮らす人間味溢れる温かい人たち。 圧倒的な歴史と文化を誇り、時に優雅で、時に間抜けで、それでいてどこか憎めないキャラクターをもちあわせる国イタリア。 たとえそれが素朴で質素であっても、こと人生を楽しむという点において「達人」といわれる彼の国の人々ですが、それが色濃く溢れているのがイタリアの南部だといいます。 そんな人々の暮らしや生き様に惹かれ、20年近くもイタリアに通いシャッターを切リ続ける写真家が加納 満(かのうみつる)さん。彼は、イタリア人の暮らしや人生を撮り続けるうちに、その傍らにいつも寄り添う愛らしいクルマ、FIAT 500の存在を意識するようになったといいます。 「そもそも僕は、「画」つまり「クルマが主体の写真」としてチンクエチェントを撮るつもりでシャッターを切りはじめたワケじゃないんです…。サルデーニャで、シチリアで、バーリで、人々やその暮らしに「出会う」のと同じように、気づくとごく自然にFIAT 500との出会いを漏らさず記録し続けていたんです。」 「情熱の赤に憧れて」 この写真展の共謀者、小野光陽(おの こうよう)さん。編集者にしてプロデューサーの彼もまた、イタリアとの縁が深い。なんといっても若い頃イタリアの情熱の代名詞ともいえる跳ね馬のエンブレムに憧れ、単身モデナに乗り込んだというツワモノ。 「ネジ一本組み付けるだけの仕事でもいいんです。それでもあのクルマたちを生み出す現場に加わりたかったんです…。」 情熱の国に相応しい熱いものをお持ちの小野さん。その後も4年以上にわたりイタリアで生活をされたという小野さん。現地の生活をよくご存知なのは言うまでもありません。 そんな彼と加納さんとの出会いは、とある雑誌の企画での偶然から。 その後も共にお仕事をなさっていたそうですが、ふとしたきっかけで加納さんのSNSに頻繁に登場するFIAT 500を見た小野さんが、この企画を思いついたといいます。 「もちろん加納さんの写真が好きだったということもあるんですが、彼の写真には、ステレオタイプで表面的なイタリアの街や暮らしではなく、僕の知っている一歩踏み込んだイタリアがそこにはあるんです…。人と街と暮らしとクルマ、そうした距離感に“これだ!”と思ったんです。」 モノは長く愛することで、愛着はもちろん心すら宿るといいますが、1957年にデビューし、その後20年に渡り製造され続けたNuova 500(ヌオヴァ・チンクエチェント)は、まさにその次元に突入しているものが多いようです。 「色あせようが、ボディやバンパーが凹んでいようが、人間が老い、顔に皺が寄るように年輪を重ねている様が、何かクルマ以上のものを僕に訴えかけてくるんです。生活や風景に馴染んで日々共に暮らしているというか。僕はそうした部分すべてを見ていただければと思っています。」 そう語る加納さん。 やっと人が通れるくらいの路地に、ありえないほど壁にギリギリに停められた濃紺チンクエチェント。加納さんとFIAT 500の「はじめの一枚」とともに、世界に愛されるイタリアの名車、今も同じくイタリア人の生活に溶け込んでいる「チンクエチェント」の真実の姿を覗いてはみませんか? 加納 満
ワンちゃんと過ごすスローライフ in 鎌倉〜ペットの健康を考える
#FIATPETS#ペット#ミニチュアダックス#ワンコ#犬ローズ一家のスローライフ スローフードという言葉が生まれたのはFIATの故郷であるピエモンテ州。ファーストフードの進出をきっかけに、もっと地元の食べ物や生活を見直そうという運動のキーワードだった。日本でもブームになり、それを実践するスローライフなる言葉も生まれたのはみなさんもご存知かもしれない。 さて今回は鎌倉でワンちゃん4匹とスローライフを楽しむ女性のお話。 安藤 愛さんは、つい最近まで大手広告代理店に勤めていた。得意の語学を活かしグローバル企業のブランディングを担当。海外相手の仕事は楽しいものだったが時差があるので勤務時間は不規則になりがちで、深夜早朝のやりとりが日常茶飯事。多忙を極める日々を送っていたとき、ミニチュアダックスフントのローズに出会う。 「ショップで抱いたときにはピンとこなかったんですが、床に置いたら私のまわりを走り回って懐くんです。その姿にキュンとしてしまって…。」 こうしてローズとの暮らしがはじまる。 生活にハリが生まれた。 しばらくするとローズの子供が欲しくなった。たくさんのワンちゃんに囲まれる生活に憧れたのは自然な流れに思えた。交配相手を見つけて、めでたく6匹の子犬が生まれた。最初は1匹を残すつもりが…。結局子供3匹とローズとの生活がはじまった。 ここまでは、愛犬家によくある話。 「ローズはなんでも食べてくれるので気がつかなかったのですが、ワンちゃんにも個性があるんですね。生まれた子供たちの中にはペットフードを食べたくない子がいたんです。いろいろ調べて、食べられるものを自分で作ればいいという結論にたどり着きました。」 研究熱心でとことん突き詰める性格は、ワンちゃんたちにとって食べやすい(食いつきがいい)だけでなく、身体にいいもの、安全なものを意識するようになる。 「ワンちゃんのために作るのではなく、自分の分まで一緒に作れば手間も時間も省けますから。」 もはや4匹はペットではなく家族だと強く自覚した瞬間だった。 そんな愛情のおかげで子犬たちはすくすくと育つ。しかし、当然ながら四六時中一緒にいられるわけではない。長期出張の際にはやはりペットホテルに頼らざるを得ない…。 それでも手作りのごはんを食べさせたかったから、業務用の真空パック機まで購入して冷凍保存したごはんをホテルに預けるようになった。 そうしているうちに、ペットホテルから他のワンちゃんたちのために、ごはんを作ってもらえないかと頼まれるようになった。 フードコーディネーターの資格を取るほど料理好きだった彼女は、ふたつ返事で引き受ける。似たような境遇のワンちゃんがいるならば、なんとかしたいと思い、材料費だけを受け取り、ほぼボランティアの形で提供したのだ。 SNSでローズたちとの生活を紹介すると、ペットホテルでの評判も手伝ってフォロワーは一気に1万を超した。それに着目した出版社がローズたちとの生活を一冊にまとめないかと言ってきたのだ。そして『おひとりさまとローズ一家』<主婦の友社刊>を2016年に上梓。ペンネームはObaba(おばば)。 気がつけばスローライフ そんな彼女の生活とくらしの価値観を変えたのは転居だった。当初はただ週末をローズたちと過ごせる海辺の家を探していた。そして広い庭のある鎌倉の一軒家を不動産屋に紹介される。 「最初、鎌倉は候補に挙がっていなかったんです。でも仲良くなった不動産会社の営業さんが、この子たちが走りまわることしか考えられない庭のある家を見つけたと連絡してくれたので(笑) もちろん一目で気に入りました。」 引っ越し後、しばらくは鎌倉から都内に通っていたが、ここでもっとローズたちとの時間を過ごしたいと思いはじめる。 実際に住んでみると、鎌倉は実に魅力に溢れる街だったということもある。たとえばレンバイと呼ばれる地元の農協が主催する朝市。 「新鮮で無農薬のものがあるんです。東京のレストランのシェフが仕入れに来るほどで味は確かですし。」 当然、ローズたちの食事にも、こういった野菜が使われるようになる。 一層ペットホテルでの評判も上がった。 「これを仕事にできればローズたちといつも一緒にいられるし、なにより同じ悩みを持つ飼い主さんの役に立てるのではないか…。」 そんな思いが頭をよぎった。 それからというもの、彼女はペットの食生活について、これまで以上に詳しく調べ、勉強するようになる。やがては自分が納得できる製品を量産できる業者選びにまでおよんだ。 「なるべく地元で採れた野菜を使い、自分が食べてもおいしいごはんを提供しよう。」 ペットたちの健康を考える他の飼い主さんの役に立てると思うとワクワクした。いや、自分が感じているワクワクを伝えたいと思った。 「運命に導かれたのかもしれません。言葉として知っていたスローライフが目の前にありました。いや、鎌倉という土地が目覚めさせてくれたのかも…。」 こうして彼女は生活のリズムをシフトダウンしはじめた。そして、会社を辞め夢の実現に奔走した。 もちろん勢いだけで仕事になるはずはない。安心感を持ってもらうためにペット食育准指導士の資格を取り、「Seaside Rose(シーサイド・ローズ)」という名でいよいよ2017年の4月からブランドをスタートさせた。 彼女が提供するのは「ペットフード」ではなく、一緒に楽しむ「ごはん」だ。出張で一緒にいられないときのものだけでなく、キャンプへ行ったとき、あるいは出かけてパートナーに「ごはん」の世話を頼まなければならないときにも役立つ。それは一緒であることを自覚できる幸せの提供だとも言える。 スローフードのコンセプトは、楽しく、朗らかに、そして健康的で元気に生きる。つまり、生活の足元をきちんとじっくりと見つめよう!ということ。 スローフード協会が選ぶ食べ物やワインやレストランなどは、いずれも価格やブランドに左右されない「本物」ばかり。 そんな国民たちの足として生み出された車、FIAT500にも同様のスローライフ精神が満ち溢れている。
世界の海を股にかけた男〜マリンイラストレーター高橋唯美
#アウトドア#イラストレーター#デザイン#ボート#ヨット周囲を大海原に囲まれた海洋国家日本…。しかし、ヨットやクルーザーなどを楽しむマリンレジャーの世界では、欧米諸国がリードしています。船舶の設え、マリーナなどの設備、そこでの時間を楽しむためのソフトウエアまで、まだまだ学ぶべき点があるようです。 イラストレーターであり、ジャーナリストとしても活躍する高橋唯美(たかはし ただみ)さんは、ヨット雑誌の最高峰「Sail」から招かれ、活動の場をアメリカのマサチューセッツ州に移したほどの経歴の持ち主。 どこか温かで、スマート…しかしスケールモデルのような緻密さを備えたその作風は、マリンレジャーで世界的な評価を受け、「Tadamiの愛称で各国のヨット、ボート関係者から愛されてきました。40年にも及ぶキャリア、200近いメーカーの訪問と350を超えるヨットやボートへの試乗など、まさに日本の第一人者と呼べる方です。 文字通り世界の海を股にかけてきたTadamiさんは、現在も江戸の香りが残る東京は八丁堀の運河のほとりで忙しい毎日を送られていますが、自宅兼事務所ビルは、裏口からそのまま愛艇に乗り込むことができるという素晴らしいロケーションで、クルージングや釣りを生活の一部として楽しむ、さすがのボートライフを送っていらっしゃいます。 たどり着いた、小さなボートでの楽しみ 小型のディンギーから100ft超の豪華クルーザーまで、長年世界の船に乗り、描いてきたTadamiさんがたどりついた愛艇は意外にも小型ボート。ボストンホエラーの17ftというモデルが現在の東京における相棒です。 「大きな船は船体だけではなくて維持費、ランニングコストいろいろかかるじゃないですか。また、80ftとかになってしまうと、一人じゃ無理。クルーが必要になるわけです。そうなると、人間関係とかマネージメントとかが面倒くさくなる。よく、大型船のオーナーさんがクルーを連れて飯に行ったりするのを見るんですが、結構気を遣ってるんですよね。大変だなあって思います。まぁ、私の人間の小ささですかね(笑)。遊びくらい好き勝手にやりたいから、一人で自由に取り回せるのになっちゃうんです。 そういうTadamiさん、沖縄の西表島と広島にもやはり、同サイズのコンパクトなボートを一艇ずつお持ちだそうで…。 「よく、小さいの3つ分で大きいのをひとつ持ったほうがいいじゃない?と言われます。でも、そのマリーナ1か所を中心とした遊び方しかできなくなっちゃうでしょ。今のようにしておくと、東京湾、瀬戸内海、沖縄…と、まったく異なった世界が楽しめるじゃないですか。 楽しい時間、心豊かな暮らしをエンジョイするという点で、彼はすでに日本人離れしているのかもしれません。 コンパクトさに込められたプライドとは… Tadamiさんは、フィアット500のファン。そのコンパクトさにこそ魅力があると言います。 「仕事で国産のボートに乗るようになってからですね。フィアット500が一層好きになったのは…。ボートに限った話ではないと思うんですが、国産のボートって小さいなりの作りしかしないんですよ。それにとても腹が立っていたんです。だって、小さいってことですでにハンデがあるわけだから、それを補う何かを与えてやってほしいんです。ちょっとリッチな感じのインテリアでもいいし、居心地のよい雰囲気でもいい…。素材やちょっとした造りとか、小さな物にこそ魂を込めてほしいと…。その点、フィアット500って、小さいという可愛いさと、シンプルだけど、みすぼらしさを微塵も感じさせない魅力を持っているじゃないですか。コンパクトであってもプライドを持って乗れるように仕上げてあるってすごいと思います。まさにあのサイズを武器にしてるとさえ思えますよね。 そんなTadamiさんが世界的なマリンイラストレーターになるきっかけは、クルマへの憧れからはじまっています。 「自動車のデザイナーになりたくて育英高専へ行ったんですね。2年後輩に由良卓也(日本を代表するレーシングカーデザイナー)君がいます。当時の製図の先生がベルギー人のすごく厳格な人で、図面に日付とか縮尺とか名前とかサインするときでさえ、必ず60度の角度で書くように指示されるんです。定規当てるよりはやいから、僕はフリーハンドでやっちゃうんだけど、そこに全部赤が入る(笑)。こりゃ向いてないな、やっぱりイラストが好きだなと確信しました。 やがてその作風は「平凡パンチ」の編集者の目に留まり、自動車のカスタムに関する連載や鈴鹿1000㎞レースのイラストルポなどを手掛け、ついにイラストレーターとしてデビューを飾ります。そして2年後、現在につながるヨット・ボート専門誌での活躍となっていきます。 セクシーさとモノづくり 自動車同様、ボートの世界でも大人気のMade in Italy。Tadamiさんは彼らのモノづくりをこう語る。 「なんともいえないセクシーさですかね。船はもちろんのこと、いろんなものやちょっとしたことにそれを強く感じますね。若いセクシーさもあれば、成熟した魅力もある。無からあそこまでセクシーなものを作り出す能力ってすごいですよ。船の世界でいうと、デッキ(甲板)のニスの塗り方ひとつにすごいコダワリがあったりするんです。 セクシーという表現は、ややもすると日本人にとっては刺激が強すぎるかもしれないが、まったくどう表現したらいいものか、日本語には適切な言葉が見当たらない…。 強いて言い換えるとするならば、なんともウキウキするようなというか、「楽しい」のちょっと先にあるオトナな感覚とでもいおうか…。もっとカワイイとステキとダンディといろんなものが混ざったものだったりする。 デッキのニスではないけれど、現行500にもいくつものセクシーさが息づいている。 「ボディの四隅やフェンダーのカーブなどはさすがだなと思わせるものだし、車内でいえばたとえばハザードスイッチなんかもそう。日本車やドイツ車のそれは文字通り緊急時のボタンでしかないんだけど、このわざわざクリア厚盛りにされたハザードスイッチは、完全に赤のアクセントとしてダッシュパネルの主役になっている。 しかも、ボディと同色のこのパネルの凹みに加担している微妙なRとか…。単に凹ませたんじゃなく、左右から緩やかになっている部分などまさにセクシーとしか言う他ない。この妖しさがイタリアンというか500の好きなところですね。」 こうした小さなオシャレの積み重ねが、Tadamiさんのいう「セクシーさに繋がっていき、シンプルなオトナの世界と可愛げのある若々しい世界の混ざり合う独特の空間を作り出しているのかもしれない。 「やっぱり、小さいけど、カワイイけど、でもやっぱりオトナなんだよなあ。500って…。 楽しい時間を知り尽くした達人がふとつぶやくその表情には、彼がはじめて乗り物の「顔」を意識させたという500同様、やわらかな笑顔が満ちあふれていた。
夢をかなえる魔法の小箱〜ライカを愛する女性カメラマン
#Leica#カメラ#写真#茅ヶ崎カメラ女子、そんな言葉を聞くようになって久しい。 デジタルカメラが普及して技術的なハードルが低くなったからだという人もいれば、インスタを例に挙げるまでもなく、写真を気軽に撮れる、もっとうまく、美しく撮りたいという気持ちは、むしろ男性よりも女性の方が高いせいなのかもしれない。いずれにせよ、カメラというメカを楽しむのではなく、写真を撮る行為自体を楽しむ女性が増えたのは事実だ。 大門美奈(だいもん みな)が、そんなカメラ女子のひとりかと言えばちょっと違うように思える。 カメラメーカーが主催する公募展の入賞をきっかけに注目を浴びるようになり写真家としての道を歩みはじめた彼女。アンダー目でしっとりとしたトーンが持ち味で、見る者の心を落ち着かせるような写真だ。もともと絵が好きで十代のころには画家に師事していたこともあった。写真との出会いは造園を学んでいた大学時代、卒論に添付する写真を撮るため一眼レフを買ったのが最初。 「ちょっと動機が不純なのですがスペインのアルハンブラ宮殿に行きたくて卒論のテーマに選びました」 照れくさそうに笑う大門。 「卒論にはポジ(スライド)を添付しなければならなかったので、なんの知識もなく一眼レフを買いました。カメラを向けシャッターを押すだけで思った通りの絵が撮れる、その不思議な感覚に写真が好きになりました」 さらりと言うが、これは大変なことだ。写真を趣味にする人の悩みの大部分は思ったように撮れないこと。よほど大門と写真の相性はいいらしい。そんな大門が写真を本格的に学びはじめたのは手痛い失敗からだった。友人の結婚式を撮り、その写真が評判を呼びその兄弟からも撮影を頼まれた。ところがカメラの設定がなにかの拍子で動いたのか、なんと何も写っていなかった。もちろん今のようなデジタルカメラではない時代なので、取り返しの付かないことになってしまったのだ。 「落ち込みました。期待に応えられなかったのが悔しかった。でも、不思議と写真をやめる気にはならなかったんです」 負けず嫌いの性格から写真専門誌のスクールに通うようになったという。 つまり趣味の延長線上という、ありがちなスタートポイントとは違い、純粋に写真の技術を磨こうという努力を行ったという点で、彼女はれっきとした正統派の写真家だといえる。 ライカとの出会い 本格的に写真を学ぶようになって大門がたどり着いた道具はライカだった。 「もちろん紆余曲折はありましたよ(笑) いろんなカメラを使ってみて、一番自分に合っていると感じたのがライカなんです」 ライカといえば世界の名機、性能も素晴らしいし出てくる絵も素晴らしい。 「もちろん、それもあるんですが一番の理由は小さくて手に馴染むからなんです」 と意外な答えが返ってきた。 「いつでも持ち歩ける相棒として、これ以上のものはないと思ったんです」 かくしてライカは大門のイメージを具現化する魔法の小箱になった。 どちらかと言えば重厚でもの静かな雰囲気を漂わせる大門の作風だが、箱庭シリーズは趣を異にする。 とある生活雑貨の店舗をジャックするかたちで行われた写真展は圧巻だった。そこには日々の暮らしを超えた、見る者を魅了する「何か」が写り込んでいた。 「最初は勤め先へ持っていくお弁当の記録だったんです。ですからスマートフォンで撮っていたんですが、そのうち満足できなくなって…。 写真が持つ一番の特性に「記録」という役割が挙げられるが、それを超えたところに表現がある。つまり被写体である弁当箱たちもまた、大門の世界を表す魔法の小箱というわけだ。だから、盛りつけにも絵心が溢れている。標本のように真上から撮られた弁当箱の中に、つい引き込まれてしまう。 ライカとFIAT 500 そんな大門だが、最近、海にほど近い神奈川県の茅ヶ崎に居を移した。 海辺の散歩が日課になり、猫との暮らしも気に入ったからだというが、この海辺の地でのライカとの散歩が、彼女の作品の幅を拡げたことは言うまでもない。しかし、一方で思いがけない問題も発生した。 「必要を感じなかったこともあるんですが、実はいままで車の免許を取らなかったんです。でも、ここへ越してきてからというもの、移動の手段として車がどうしても必要。だから運転免許取得を真剣に考えるようになったんです…。 そんな大門をFIAT 500の助手席に乗せて海辺の道を走ってみた。 「クルマは好きなんです。流れる風景を眺めるのも好き。どこかへ運んでくれるメカっていうのもいいですね。それに、これ小さくてかわいい。なんだかライカみたい。 大門の愛機であるライカM10は、1954年に誕生したレンジファインダーの名機ライカM3の末裔。ほぼ同時期の1957年に生まれたNuova 500と現行の500との関係にも共通点がみられる。 ライカM3とはアナログのカメラの金字塔的な存在であり、その子孫たるライカM10は、その佇まいはもちろんのこと、使い勝手やコンパクトネスなどをライカM3から引き継ぎ、そこにデジタルの便利さを兼ね備える名機として、今も大きな人気を誇る。 まさに新旧500とよく似た境遇の存在でもある。 「実は鎌倉あたりでよく見かけるので、いいなぁって思っていたんです。道の狭い小ぢんまりとした街にも似合っていてお洒落だし…。
おでかけFIAT〜小さな高級魚ワカサギにみる「小粋」という価値
#おでかけ#アウトドア#グルメ時代が求める小さな美味 SNSの発展とともに、かねてからのグルメブームはさらに加速しました。とりわけ高級肉などが好例ですが、同じくらいの人気を集めるのが「お魚さん」。大間のマグロ、氷見のブリ、日本海のノドグロなどなど、その多くは脂の乗りを身上とする、派手な顔ぶれがほとんど。確かに美味い。間違いなく幸せなおいしさがそこにはあります。 ところが、そうした重量級のスターたちに負けず劣らずの支持を受けているのが、たとえば琵琶湖のホンモロコ。長く小さな高級魚として食通の間で珍重されてきたのですが、最近では若い女性の間でも流行の古都の旅で、虜になる人が続出しているとか…。その需要を受けて各地で養殖も始まったといいますから、ちょっとしたブームの予感すら感じられます。 ギラギラとした豪華さや派手さばかりが上質ではない! という流れが世界的に巻き起こる現在、自然に人々は真の豊かさやモノの本質に、以前よりも気をとめるようになったのかもしれません。 魚に限らず、こうした個性的でキラリと光るキャラクターをもつ食材や料理に対する注目度は、これからさらに上がるでしょうし、むしろちょっと小粋でオシャレにすら映るのかもしれません。 さて、今回は、同じように人差し指ほどの姿でありながら、徳川家の将軍を虜にし、天皇に捧げられた魚…。「ワカサギのお話です。 えっ?ワカサギが? そう思う方も多いでしょう。スーパーでも魚屋でもごく普通に売られていて、甘露煮や南蛮漬けなど惣菜店でもおなじみのアノ魚です。 ワカサギは「公魚」と書き、第11代将軍徳川家斉の時代、霞ヶ浦に近かった麻生藩はワカサギを年貢として献上することが許されていました。つまり、公儀御用の魚=「公魚」というわけなのです。“小さな高級魚”として江戸幕府の将軍たちはこの美味に目を細めていたのです。 今も箱根に残る「献上公魚」 今や世界的な観光地として人気も高く、年間2000万を超える人々が訪れる箱根。その地の中心にある芦ノ湖は、蒼い湖面に朱の鳥居が映え、霊峰富士山を臨む美しい湖ですが、ここで育ったワカサギは、刺網漁が解禁となる毎年10月1日に、天皇陛下、皇太子、秋篠宮、常陸宮の各宮家へ献上されているのをご存知でしょうか? 皇室の避暑地として「函根離宮が置かれていたこともあって、昭和天皇はことのほか箱根を愛していました。そして、昭和24年の植樹行事をきっかけに献上が始まったという経緯があります。 採捕されたワカサギは同湖の漁業協同組合により、湖畔にある九頭龍神社へ奉納され、午前7時から公魚献上奉告祭を迎え、やがて皇居内の宮中三殿と呼ばれる三つの神殿へ向けて旅立っていきます。 そんなワカサギは、一方で実は誰もが簡単に気軽に楽しめる釣りのターゲットでもあります。その大きさからは想像がつきにくいのですが、実はサケの親戚なので好奇心が非常に強く、闘争心も旺盛。可憐な姿に似あわず、群れの中で激しく餌を奪いあったり、光るものや動くものに激しく反応するので、芦ノ湖では餌をつけずにハリだけでも釣る事が可能。ふらりと手ぶらで訪れ、道具をレンタルし簡単に楽しめる手軽さも芦ノ湖のワカサギの魅力です。 小さな身体に潜む奥深い味わい 甘露煮や佃煮も有名ですが、フライや天ぷら、素焼きといったシンプルな調理法やアレンジでこそワカサギの素材力が浮き上がってきます。 炭火でじっくりと炙っていくと、さらりとした上品な味の脂がにじみ、やがて皮の焼ける甘い香りが立ちのぼり、噛みしめるときめ細やかな身がフワっとほぐれていきます。あっさりとしているのに、じんわりと広がっていく旨み…。その他ピザに載せたりなどしてもとても美味しいワカサギ。ドライブのついでや日帰りキャンプに是非ともお試しいただくことをオススメします。 肩肘を張らないという特技 そんなワカサギにまつわる話には、日本人とイタリア人の間にある共通点を見出すことができます。美や歴史、何より食を重んじるところはもちろんなのですが、派手さにとらわれず、ちょっとしたコトやモノにも価値を見出す「小粋」という感覚を持ち合わせることがその最たるものかもしれません。 北に上質なポルチーニがあると聞けば北へ、最高のピスタチオがあると聞けば南へと躊躇なく数百キロも走るイタリア人は、本当の上質が意味するものが何なのかを身体で知っています。 四季折々、各地方の田舎町の名産を嗜むのは最高の贅沢として広く一般的ですが、戦後のイタリア人にそれを体感させたのは、他でもないFIATの小型車たちなのです。 街からアルプス、城塞都市や農道など、あらゆる景色に自然に溶け込むデザインを持ちあわせる小さな相棒たち。多彩な景色や文化、なにより豊富な食文化を持つ日本にも自然にフィットするはずです。 さあ、あなたもFIATで日本を味わい尽くしてみませんか? 参考文献 九頭竜神社社報
オーナー紹介〜イタリア文化を丸ごと愛する2人の思いが、トラットリアと500に凝縮!
#オーナー紹介#グルメ#レストラン文=田代いたる(ベスト・イタリアン選考委員) 写真=太田隆生 店で使うおしゃれな備品を500で買い出し 真っ赤なボディに、ベージュのソフトトップが何ともスタイリッシュな500Cが、この日、『IKEA立川』のパーキングにありました。オーナーは竹内悠介さんと舞さん夫妻。ペーパーナプキン、ストロー、フォトフレームなど、今日もたくさんお買い上げのよう。『IKEA立川』には「よく来ます」と笑顔で舞さん。竹内さんも、「店で使っているテーブル周りの備品など、いつもここで買っています。イタリアに住んでいた頃から愛用していますよ」と続けます。竹内さんは、西荻窪で人気のイタリア料理店『トラットリア29(ヴェンティノーヴェ)』のオーナーシェフです。 『トラットリア29』は肉料理が評判の、西荻窪の人気店 愛車を走らせ、店に戻った竹内さん。舞さんにも手伝ってもらい、ディナータイムの準備に取りかかります。『トラットリア29』は今年で7年目。当初から変わらないコンセプトは「お肉の美味しいイタリアンレストラン」。メインはもちろん、前菜やパスタも肉料理がズラリ。その原点は竹内さんが修行したトスカーナ州にありました。 「けれど、最初の修行先にトスカーナを選んだ理由は、当時、自分の中にイメージができたイタリアで唯一の州だったから。本当に、そんな程度(笑)。元々、肉料理は好きで『州都のフィレンツェもビステッカが名物だからなぁ』って。何のツテもなく、行ってしまいました」。 最初の修業は、ビザの関係から半年の期間限定でした。「運良く、日本人シェフが在籍していた、フィレンツェの店で働くことはできたのですが、半年では全然、足りなかった。そこの先輩料理人から、存在を教えてもらったのが『チェッキーニ』でした」。そこである日、見学に出かけることに。 イタリアで『チェッキーニ』と出逢い、肉にのめり込む 『チェッキーニ』とは、トスカーナ州パンツァーノで400年(!)も続く老舗の精肉店。生の肉を卸し、販売するだけでなく、生ハムやサラミ、牛肉のタルタルなど、肉の総菜もいろいろ扱っています。店の向かいにはビステッカが名物の直営レストランも併設。竹内さんも驚いた、肉尽くしの環境がそこにはありました。 「生から熟成まで、肉料理に、これほど多彩なアプローチがあるのかと感激しました。その奥行の深さにすっかり魅せられてしまった」。 竹内さんがここで実感したのはひとつの文化。主役は肉で、町のお肉屋さんがその文化を牽引し、多くの人から愛され続けている。「いつかは自分の店を持ちたい」。イタリア料理の世界に飛び込んだときから抱いていた、竹内さんの漠然とした夢は『チェッキーニ』と出逢い、確固たる信念に変わりました。 「肉に特化した店をやる」。強い決意を胸に抱き、改めてイタリアへ渡った竹内さん。ほかの州も知っておきたいと、今度はエミリア・ロマーニャ州ボローニャで著名な『トラットリア・ダ・アメリーゴ』や、マルケ州で城壁の内にあるリストランテ『ラ・ボッテ』といった名店で研鑽を積みます。一方で、『チェッキーニ』にはずっと修業を嘆願。望みが叶ったのは、渡伊から1年半の月日が経った頃でした。 肉漬けの日々で見えてきた、肉の本当の美味しさ 「『チェッキーニ』では本当に、朝から晩までみっちり、肉(笑)。毎日7時から午前中はずっと、70歳を越える熟練職人の隣で肉を解体して、ランチタイムはレストランの手伝い。夜は夜で、また肉屋に戻って作業する。おかげで、それぞれの部位にはどんな特性があって、どういう調理が適しているのか、深く知ることができました」。 だから『トラットリア29』のビステッカは、イタリアで感激した赤身の美味しさを真っ直ぐに伝えるスペシャリテ。調味は基本的に焼き上がりに振る塩のみで、熱源も炭火。『チェッキーニ』と同じスタイルを踏襲しています。 「表面の水分を適度に飛ばして香ばしく、中はレアに仕上げるイメージ。時間はかけず、一気に焼き上げる。今日の短角牛で300gほどですが、完成まで10分ぐらい。日本で塊肉だと休ませながら焼くというイメージがありますが、イタリア人に言わせると、『それはビステッカでなく、ローストビーフだ』って言われてしまう(笑)」。 奥様との出逢いももちろん、イタリア! 『トラットリア29』は、イタリアの食文化に惚れ込んだ、竹内さんの熱意が凝縮されたレストラン。今も、年に1回は現地へ。そこで体感し、会得した、すべてが血となり肉となってお店に結実しているのです。実は、この日も2週間ほど滞在したフィレンツェから戻ったばかり。今回も、少なからず新たな発見があったようです。「新しい写真を飾らないと」。笑顔で舞さんが言いました。 そう言えば、竹内さんと舞さんが初めて出逢ったのもフィレンツェだったのでは? 「実は、よく食べに行っていた『トラットリア・ソスタンツァ』の裏手に、妻と横内美恵さんが暮らしていた部屋があって。横内さんを介して知り合いました」 横内さんは、今、『トラットリア29』の店舗を使い、別業態としてランチ限定で営業する、サンドウィッチ専門店『3&1(トレ・エ・ウーノ)』の責任者。竹内さんがフィレンツェで初めて働いた店の後任が、横内さんという縁があります。当時、彼女のルームメイトとして一緒に暮らし、ジュエリーデザインの学校に通っていたのが、舞さんでした。 舞さん曰く、「この店のデザインは、私の美大時代の先生にお願いしました。もちろん、2人のアイデアはいろいろとリクエストしています。そして、小物などを集めて飾るコーディネートは私の担当。飾る写真などは、折に触れて替えています」。 イタリア人のデザイン力に惹かれて なるほど、明るくスタイリッシュな店内は、夢を叶えてジュエリーデザイナーとしても活躍する舞さんと、竹内さん、そして美大時代の恩師のセンスの賜物。伝統的で重厚な肉料理を提供するするレストランとは思えないほど、洗練されています。実はその理由も「『チェッキーニ』の存在が大きかった」と舞さんは振り返ります。 「歴史があるお店なので、建物自体は何百年も前に建てられたままですが、『チェッキーニ』のレストランは、中に入るとビックリするぐらい、モダンにリノベーションされていた。彼らチームのデザイン力を実感しました。帰国して、店を始めるとき、最初から、そういう風にしたいねって2人で話していました」。 聞けば、トスカーナ州の代表的ワイン、キアンティの品評会でも、古い駅舎を会場に使用。外観は荘厳に、中は明るくモダンなんてことがよくあるそう。イタリアは美食の国であると同時にデザインの国でもある。そんなことを改めて思い出します。そして、竹内さんが愛車に500Cを選んだのも、イタリアへの愛の深さを考えれば、当然のことでした。 500のためのドライバーズライセンス 「ちょうど、僕がボローニャで修業していた頃、500に3代目が誕生して、街で見る度に『乗りたいなぁ』って思っていました。免許もなかったのに(笑)。イタリア人の同僚に『買ったぜ』と自慢されたときはホント、悔しかったなぁ」。 だから、運転免許取得の動機はただ一途に「500に乗りたかったから」。忙しい合間に免許を取って、店が軌道に乗った3年半ほど前にようやく、500Cを購入しました。買い出しでも大活躍する、今や『トラットリア29』には欠かせない、大切な存在です。 「かわいくて選んだカラーリングですが、後から見るとベージュが脂、ボディが赤身で、やっぱり肉になっているんです(笑)」という竹内さんに、舞さんは「彼はいつもそう言うんですけど、誰も同調してくれない(笑)」。 イタリア文化を丸ごと愛する2人の熱い思いが、『トラットリア29』の料理と店舗、そして500Cに凝縮されています。
オーナー紹介〜ウェディングのメインゲストは500
#オーナー紹介#ルパン三世文=田代いたる 写真=太田隆生 転勤で同じ事業所になった同僚と結婚 仲睦まじく、箱根『小田急 山のホテル』のテラスでスイーツを楽しむカップル。影山僚大さんと悠里加さんは、今年6月に結婚式を挙げたばかりの新婚カップルです。共に同じ会社に勤務。3年前、僚大さんが北海道から悠里加さんのいる神奈川の事業所に転勤してきたことで出逢い、今日に至りました。最初のデートから「優しくて素敵な女性だなと感じました」と僚大さんが言えば、悠里加さんは「しっかりしていて引っ張っていってくれる、自分とは真逆のタイプ」と応えます。そんな2人がこの日、乗ってきたクルマがバニライエローの500。悠里加さんの愛車です。 500との出逢いは小学3年生 その優しいカラーリングのほかにも、車内には花も飾られて女性らしい雰囲気。かわいくディスプレーされた大小のミニカーからは悠里加さんの500への強い愛を感じます。 「小学校3年生のときに、ルパン三世の映画『カリオストロの城』を見たんです。そのとき、ストーリーよりクルマのかわいさに驚いて、ひと目惚れしちゃいました。500のミニカーを集め始めたのはその頃からですね」。 現在、20台はコレクションがあるとのこと。バレンタイン限定のミニカー付きチョコレートは毎年、欠かさず購入しています。 「僕はそのチョコ、もらったことないなあ(笑)」と僚大さん。「いつも自分で買って自分で食べちゃうから(笑)。来年はプレゼントしようかな」。 2人それぞれ、別々のイタリア車 実は悠里加さんの500に対して、僚大さんの愛車はAlfa Romeo MITO。1人1台のクルマを所有しています。MITOを選んだ理由を「妻の“500愛”に影響されました」と振り返る僚大さん。結婚を決意した後で夫婦のクルマとしてまず購入したそうです。 「展示会で見た瞬間、カッコいいなぁと(笑)。その日のうちに契約しちゃいました。妻のお陰でイタリア車に対する理解が深まっていたのだと思います。だから、妻にも『そんなに好きなら、もう1台、買ってもいいんじゃない?』って提案しました。探していたら国立のディーラーさんに、状態の良いバニライエローの500があった」。「一緒に見に行ってすぐに、『あ、買います』(笑)。私も、即決でした」と悠里加さん。 500も一緒に、箱根のリゾートホテルで挙式 2台あるから「その日の気分に合わせて乗り換えられえる」と小春日和のテラスで幸せそうに語る2人。実はここ、『小田急 山のホテル』は夫妻が結婚式を挙げた舞台でもあります。「景色がキレイ」と悠里加さんが見つけてくると、僚大さんも「歴史があるし、その風格に魅せられました」と納得。 「でも最大の決め手は何より、スタッフの方々。本当に親切にしてくださって」。当日は何と、チャペルに500を運び入れて記念写真も撮りました。中にはトリックアートのような一枚もあり、「あのときは腰が痛かった」と僚大さん、思い出し笑い。夫婦になってからも撮影も兼ね、500でいろいろな場所へ出かけています。 北海道を500で巡って 「今年の夏休みは僕の実家がある北海道へ、500に乗って帰省しました」。運転は主に僚大さんでしたが、「キビキビとスムーズに走れて気持ち良かったです」と言います。500で帰った理由については「私が説得しました」と悠里加さん。「北海道の景色をバックに、500の写真が撮りたいって思って。『メルヘンの丘』のような大自然の中でどれだけ映えるか、見たかった。いっぱい撮影してみて私が実感したのは、500はどんな場所でも絵になるということ。それが一番の魅力かもしれません。500を買ってからは、出かけることも増えたよね?」 「そうだね。今は、目的地でなく『この辺りをドライブしたい』って最初に考えるようになりました。500に乗るようになって、出かけるきっかけが変わりました」。僚大さんもフォトジェニックな500の魅力を認めているようです。 不安を払拭してくれたディーラーの心遣い 悠里加さんが長年の夢を叶えて500を購入したのは今年4月。最初は「自分でちゃんと運転できるか、少し心配だった」と言います。けれど、ディーラーの対応が素晴らしく、すぐに安心できたそう。 「納車日に、デュアロジックの操作方法などを教えてくれるために、後ろに乗って一緒にドライブしてくださったんです」と僚大さん。「おかげですごく助かりました」と悠里加さん。「そんなに運転は得意な方じゃないけど、初めて乗ったときから、私の体にフィットして、手足のように動いてくれる感覚がありました。自分に合っていると思います。女性でも気軽に乗れるクルマですね」と操作性の魅力も体感しているそう。さらに「服装でお洒落するようにクルマもお洒落な方が楽しいと思うんです」。これには僚大さんも同感。「僕もクルマ選びには、自分の中のこだわりを反映したつもりです」。2人の絆は、同じ価値観を共有することでも深められています。 新居の完成を待つ2台の愛車 「今の500は廃車になったとしても、庭にずっと飾っておきます!」と溢れる“500愛”を語る悠里加さん。現在2人は来春の完成予定で、一軒家の新居を計画中。「ミニカーのショーケースとか、業者さんといろいろなアイデアを詰めている段階」だと言います。「最初はスペースの有効活用で縦列を予定していたんですけど、『お互いのクルマがちゃんと見えた方がかわいいよね』と意見が一致。結局、無理矢理、横に並べられる駐車場をお願いしました」と僚大さんも笑っています。 さらにもう一つ、2台がリビングから見えることもリクエストしているそう。悠里加さん曰く「ご飯を作りながら、ソファに座りながら、いつでも眺めていたいから」。新居に並ぶ2台の愛車はきっと、2人の幸福を象徴する存在になることでしょう。 『小田急 山のホテル』 芦ノ湖と富士山、箱根の絶景が楽しめるリゾートホテル。広々とした庭園はツツジ、アジサイ、バラ、紅葉など、四季折々の植物を楽しめることで有名。また寛ぎの場として愛され続けてきた1階にある「ラウンジ・バー」では、正統派の「アフタヌーンティー」やホテル特製スイーツなどが楽しめる。2017年11月12日までは、「箱根スイーツコレクション2017秋」参加スイーツ「秋季箱」(本文参照)を提供。 SHOP DATA 店名 『小田急 山のホテル』 住所 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80 電話番号